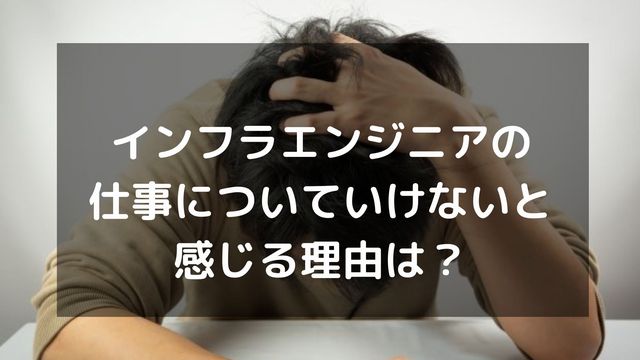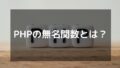「突発的な障害対応や夜勤続きで、体力的にも精神的にも限界だ」
インフラエンジニアとして働いている中で、このように「仕事についていけない」「もう辞めたい」と悩む人も多く存在します。
IT社会の基盤を支えるインフラエンジニアは、需要が高い一方で、その責任の重さと業務範囲の広さから、離職を考える人が多い職種でもあります。
しかし、「ついていけない」と感じるのは、能力不足だけが原因ではありません。
業界特有の構造や、職場環境のミスマッチが大きな要因となっているケースが非常に多いのです。
そこでこの記事では、なぜインフラエンジニアが「仕事についていけない」と感じてしまうのか、その具体的な理由を深掘りし、現実的な対処法を紹介していきます。
 |
|


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!
インフラエンジニアが仕事についていけないと感じる理由

インフラエンジニアが仕事で直面する困難は多岐にわたり、その厳しい現実は、多くのエンジニアを疲弊させる原因となり得ます。
ここでは、「もうインフラエンジニアの仕事についていけない」と感じてしまう具体的な理由を、8つ紹介していきます。
夜勤や休日の出勤がつらい
ITインフラは、社会や企業の活動を支えるため、24時間365日、常に安定して稼働し続けることが求められます。
そのため、インフラエンジニアの働き方は、システムの監視やメンテナンスのためにシフト制の夜勤や休日出勤が避けられないケースが少なくありません。
システムの定期メンテナンスやリプレース作業は、ユーザーへの影響が最も少ない深夜や休日に行われるのが一般的だからです。
友人や家族と生活リズムが合わず、プライベートな時間を確保しにくいことは、精神的な孤立感やストレスに繋がりやすいでしょう。
突発的なトラブルがあったら解決するまで帰れない
インフラエンジニアにとって避けられないのが、突発的なシステム障害への対応です。
したがって、一度トラブルが発生すれば、原因を特定し、システムを完全に復旧させるまで職場を離れることは許されません。
深夜に鳴り響く障害アラートの電話で叩き起こされ、そのまま徹夜で対応にあたることも珍しくないのです。
いつ終わるか分からない障害対応は、肉体的にも精神的にも極度の緊張状態を強いられ、「もうついていけない」と感じる大きな要因となり得ます。
インフラは「正常に機能して当たり前」だと思われている
電気や水道と同じように、ITインフラは「動いていて当たり前」と社会全体から認識されています。
インフラエンジニアが日々、地道な監視やメンテナンスを行い、システムの安定稼働を維持していても、それが特別に評価されたり、感謝されたりする機会はほとんどありません。
しかし、ひとたび障害が発生すれば、「なぜ問題が起きたのか」「どうしてくれるんだ」と厳しい責任追及を受けることになります。
この歪んだ評価体制が、縁の下の力持ちであるインフラエンジニアのモチベーションを著しく低下させ、やりがいを見失わせる原因となるのです。
覚えなければいけないことが多く進化スピードも速い
インフラエンジニアの守備範囲はかなり広く、覚えなければいけないことも多いです。
かつてはサーバーとネットワークの基礎知識があれば通用しましたが、現在は環境が激変し、以下のような知識・スキルを幅広く求められる傾向にあります。
- オンプレミス知識(物理サーバー、配線、L2/L3スイッチなど)
- OS・ミドルウェア(Linux、Windows Server、DB、Webサーバーなど)
- クラウド(AWS、Azure、GCPなど)
- コード化・自動化(Terraform、Ansible、Docker、Kubernetesなど)
こういった知識やスキルを、業務と並行しながらキャッチアップし続ける必要があることから、「どれだけ勉強してもゴールが見えない」という徒労感に繋がり、「ついていけない」と感じてしまうことがあるのです。
業務がルーチン化しやすく成長が実感できない
インフラエンジニアの業務は、大きく「設計・構築」と「運用・保守」に分かれます。
特に運用・保守フェーズを主に行う職場の場合、日々の業務が、
- システムの監視
- 定型的なオペレーション
- 問い合わせ対応
・・・といったルーチンワークに終始してしまうことがあります。
もちろん、これらは安定稼働を支える重要な業務ではありますが、毎日同じことの繰り返しでは、新しいスキルが身につかず、自身の成長を実感しにくいものです。
「このままで、自分の市場価値は上がるのだろうか」というキャリアへの不安は、仕事へのモチベーションを削ぎ、ついていけないと感じる一因となり得ます。
人手不足の会社では残業が常態化する
IT業界全体が人手不足に悩んでいますが、特にインフラ領域は専門性が高いため、人材の確保が難しい状況にあります。
経済産業省の調査でも、IT人材の不足は指摘され続けており、2030年には最大で約79万人のIT人材が不足するとの試算もあります。
(出典:経済産業省「IT人材育成の状況等について」)
少人数で広大なインフラ全体を管理しなければならず、日常的な運用業務に加えて、新規プロジェクトや障害対応が重なると、あっという間にキャパオーバーに陥ります。
結果として、恒常的な長時間労働や休日出勤が常態化し、心身ともに疲弊してしまうのです。
生活リズムが安定せず体調を壊しやすい
夜勤やシフト勤務、そして深夜・早朝を問わない緊急の呼び出し。
このように、インフラエンジニアの勤務形態はどうしても不規則になりがちです。
不規則な生活が続くと、睡眠時間や食事の時間がバラバラになり、生活リズムが大きく乱れてしまいます。
心と体は繋がっているため、身体的な不調は、やがて気力の低下や集中力の散漫といった精神的な問題にも発展し、「もう頑張れない」という状態に陥りやすくなるでしょう。
業務に対する責任が重い
インフラエンジニアが扱うシステムは、企業の事業活動の根幹そのものです。
もしインフラに重大な障害が発生すれば、ECサイトでの販売機会を失ったり、工場の生産ラインが停止したりと、数時間で数億円規模の損害が発生することも決して大げさな話ではありません。
また、セキュリティインシデントを引き起こせば、企業の社会的信用を失墜させる事態にもなりかねません。
自分の操作一つが、会社全体に計り知れない影響を与える可能性があるという事実は、常に重いプレッシャーとしてのしかかります。
この過大な責任感が、精神的な負担となり、仕事についていけないと感じる大きな要因となるのす。
インフラエンジニアに向いていない人の特徴
こんな自問自答をしている方も少なくないでしょう。
そこで、以下に「インフラエンジニアに向いていない人の特徴」をまとめました。
継続的な学習が苦痛な人
業務時間外でも新しい技術をキャッチアップすることに興味が持てない。
不規則な生活に弱い人
夜更かしが苦手、または生活リズムが崩れるとすぐに体調を崩してしまう。
目に見える成果物が欲しい人
Webデザインやアプリのように、自分の作ったものが華やかに動くことに喜びを感じる。
常に100%の正解を求めてしまう人
トラブルシューティングには、マニュアルにない臨機応変な対応や、「とりあえず動かす」という判断が求められる場面もある。
大雑把すぎる性格の人
100%の正解を求める完璧主義もよくないものの、大雑把すぎるのも駄目。設定ファイルの1文字の間違いも許されないため、細かい確認作業が苦手な人は重大なミスを起こすリスクがある。
逆に言えば、「技術は好きだが、夜勤だけが辛い」「ルーチンワークは嫌だが、構築は楽しい」という場合は、インフラエンジニアという職種自体は向いています。
その場合の問題は、「職場環境」にありますので、他の会社への転職や、フリーランスとしての独立など、環境を変える行動が有効でしょう。
インフラエンジニアが「仕事についていけない」と思った時の対処法

「もう限界だ」「ついていけない」と感じても、すぐにキャリアを諦めてしまうのは早計です。
インフラエンジニアは、大変な部分もありますが、その分やりがいも多い仕事です。
現状を悲観するのではなく、具体的なアクションを起こすことで道は開けます。
ここでは、現状を打破するための5つの具体的な対処法を紹介します。
インフラに関する既存スキルを高める
「ついていけない」と感じる原因の一つに、基礎知識やスキルの不足からくる自信のなさが挙げられます。
日々の業務に追われ、断片的な知識で対応していると、応用が利かず、トラブル発生時にパニックに陥りがちです。
まずは一度立ち止まり、基礎を体系的に学び直すことをお勧めします。
- Linux: コマンド操作やシェルスクリプト、OSの仕組みを改めて学習する。
- ネットワーク: TCP/IPの階層モデルや主要なプロトコルの役割を深く理解する。
これらの基礎が固まることで、自信がつき、トラブルシューティング能力も格段に向上するでしょう。
LPICやCCNAといったインフラ関連の資格の取得を目指すのも、知識を体系化し、スキルを客観的に証明する上で非常に有効な手段です。
新たなスキルを習得する
基礎を固めた上で、現在の市場で求められる新たなスキルを習得することは、自身の価値を高め、仕事の幅を広げる上で極めて重要です。
特に以下の3つの分野は、今後のインフラエンジニアにとって必須と言えるでしょう。
これらの新しいスキルを身につけることで、ルーチンワークから脱却し、より高度でやりがいのある業務に挑戦する機会が得られます。
メンタルケアの方法を学ぶ
インフラエンジニアの仕事は、責任の重さや不規則な勤務から、心身に大きなストレスがかかりやすいです。
したがって、技術スキルと同様に、自分自身の心を守るためのセルフケア能力も非常に重要です。
自分に合ったストレス解消法を見つけ、意識的に実践してください。
例えば、以下のような方法があります。
- 適度な運動:ウォーキングやジョギングなど、軽い運動を習慣にする。
- 趣味に没頭する時間:仕事のことを完全に忘れられる時間を作る。
- 十分な睡眠:質の良い睡眠を確保する工夫をする。
- 信頼できる人に相談する:家族や友人、同僚など、悩みを打ち明けられる相手を持つ。
もし、自分一人で抱えきれないほどのストレスを感じている場合は、決して無理をせず、会社の相談窓口や専門のカウンセラー、心療内科といったプロの助けを借りることも、大切な選択肢の一つです。
自分が望む働き方ができる会社に転職する
もし「ついていけない」原因が、個人のスキル不足ではなく、会社の労働環境や文化にあるのなら、環境そのものを変える、つまり転職が最も有効な解決策となります。
同じインフラエンジニアでも、会社によって働き方は全く異なります。
- クラウド技術を積極的に採用している企業
- SRE文化が根付き、自動化や効率化を推奨している企業
- ワークライフバランスを重視し、夜勤や休日出勤が少ない企業
上記のような、自分が望む働き方ができる会社へ移ることで、悩みは解決するかもしれません。
しかし、優良企業を自力で見つけるのは困難な場合もあります。
そこで活用すべきなのが、IT業界に特化した転職エージェントです。
こういった転職エージェントサイトを利用して転職先を探すのも、仕事についていけない時の対策法として有効です。
フリーランスのインフラエンジニアになる
十分なスキルと実務経験、そして自己管理能力に自信があるならば、会社員という枠を飛び出し、フリーランスとして独立する道も考えられます。
フリーランスになれば、会社員時代にはなかった自由な働き方を手に入れることが可能です。
働く時間や場所、休日を自由に決められるだけでなく、使用する技術やプロジェクトの内容も、自分の意向で選択できます。
そのため、ストレスに関しては大幅に減らせる可能性が高いでしょう。
こうした不安を抱えている方もいるかもしれませんが、今では転職エージェントだけでなく、フリーランスに最適な案件を無料で紹介してくれる「フリーランスエージェント」というサービスもあります。
代表的なフリーランスエージェントには、以下のようなものがあります。
- レバテックフリーランス
(週5でコミットできる高単価案件多数)
- Midworks
 (週1~3日からの副業案件もあり)
(週1~3日からの副業案件もあり) - フリーランスボード
 (無料登録をするだけスカウトが来る可能性あり)
(無料登録をするだけスカウトが来る可能性あり)
こうしたサイトを利用することで、自分にマッチした案件を早期に獲得することが可能となるでしょう。
インフラエンジニアとして後悔しないためのポイント

これからインフラエンジニアを目指す方や、キャリアチェンジを検討している方が、入社後に「こんなはずではなかった」と後悔しないために、事前に知っておくべき3つの重要なポイントを解説します。
どのようなメリット・デメリットがあるのか把握しておく
インフラエンジニアという仕事には、光と影の両面があります。
その両方を客観的に理解しておくことが、ミスマッチを防ぐ第一歩です。
| メリット | デメリット |
| ■IT社会を根幹から支えている実感を得られる ■ITが存在する限り需要がなくならず職に困る可能性が低い ■幅広い知識が身につく |
■責任が非常に重く、精神的なプレッシャーが大きい ■夜勤や休日対応など、不規則な勤務形態になりやすい ■常に最新技術を学び続ける必要がある |
これらのメリット・デメリットを天秤にかけ、自分にとってこの仕事が本当に魅力的かどうかを冷静に判断してください。
十分なスキルを得てからインフラエンジニアとして就職する
インフラエンジニアの学習範囲は非常に広いため、全くの未経験からこの世界に飛び込むと、知識の吸収が追いつかず、早々に挫折してしまうリスクが高いです。
入社後に苦労しないためにも、就職・転職活動を始める前に、基礎的なスキルを身につけておくことを強く推奨します。
プログラミングスクールやオンライン学習プラットフォーム、あるいは独学で、最低でも以下の知識は習得しておきましょう。
- Linuxの基本操作とサーバー構築の基礎
- ネットワークの基礎(TCP/IP、ルーティングなど)
- 可能であれば、AWSなどのクラウドサービスの初歩的な知識
これらの土台があるだけで、入社後の学習効率や業務への適応度が格段に変わってきます。
なお、インフラに強いプログラミングスクールでスキルを高めたい場合は、ウズウズカレッジが最適でしょう。
求人へ応募する前に企業研究を徹底的に行う
「インフラエンジニア」と一括りに言っても、所属する企業によってその業務内容や働き方は千差万別です。
以下の点を重点的にチェックしましょう。
- インフラ環境(オンプレミス中心か、クラウド中心か)
- 業務内容(設計・構築フェーズに関われるか、運用・保守がメインか)
- 働き方(夜勤やシフト勤務の有無、緊急対応の頻度や体制)
- 企業文化(SREやDevOpsの考え方が浸透しているか)
求人票の情報だけでなく、企業の技術ブログや社員のSNS、転職エージェントから得られる情報、口コミサイトなどを多角的に活用し、その会社で働く自分の姿を具体的にイメージできるまで、深くリサーチすることが後悔しないための鍵となります。
まとめ
インフラエンジニアが「仕事についていけない」と感じてしまうのは、決して能力だけの問題ではありません。
職種の特性や、広大で進化の速い技術領域、そして会社によっては過酷な労働環境など、様々な要因が複雑に絡み合っています。
大切なのは、現状を一人で抱え込んで悲観するのではなく、具体的な行動を起こすことです。
職場環境に問題があると感じた場合は、できるだけ早く、転職エージェントやフリーランスエージェントを活用して、働く環境を変えてみることをおすすめします。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!