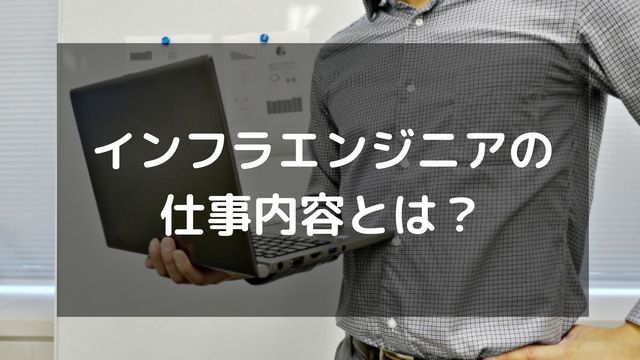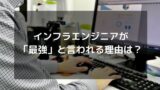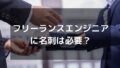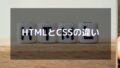「インフラエンジニア」という仕事に興味があるものの、「具体的にどんな仕事内容なのか」「なんだか難しそう・・・」と感じて、敬遠している方もいるでしょう。
インフラエンジニアは、私たちが毎日利用するWebサイトやアプリケーション、メールといったITサービスの基盤を設計・構築し、その安定稼働を支える専門家です。
表舞台に出ることは少ないものの、現代のデジタル社会においてその重要性はますます高まっており、まさに「縁の下の力持ち」と言える存在です。
この記事では、そんなインフラエンジニアの仕事内容について、初心者の方にもわかりやすく具体的に解説します。
その他インフラエンジニアになるための必要スキル、将来性、キャリアパスなどについても紹介しますので、是非参考にしてください。
 |
|


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!
【まずは概要】インフラエンジニアとは?

インフラエンジニアとは、ITシステムの基盤となる「インフラストラクチャー」の設計、構築、運用、保守を専門とする技術者のことです。
普段、Webサイトやアプリケーション、メールなどが、24時間365日いつでも安定して使えるのは、インフラエンジニアがその土台を支えているからにほかなりません。
家を建てる際に、まず土地を整備し、電気や水道、ガスといったライフラインを整えるのと同じように、ITシステムにおいてもサーバーやネットワーク、データベースといった基盤が不可欠です。
インフラエンジニアは、まさにこのITにおけるライフラインを整備し、維持管理する重要な役割を担っています。
その業務は、新しいサービスを立ち上げる際のインフラ設計・構築から、稼働中のシステムが止まらないように監視・メンテナンスする運用・保守まで多岐にわたります。
目に見えるアプリケーションを開発するわけではありませんが、ITサービス全体の品質や安定性を左右する、非常にやりがいのある職種です。
インフラエンジニアの種類

「インフラエンジニア」の括りの中にも、専門領域によっていくつかのエンジニアに分かれています。
それぞれの職種が連携し合うことで、堅牢なITインフラが成り立っているのです。
ここでは、インフラエンジニアとして代表的な4つの職種を紹介していきます。
サーバーエンジニア
サーバーエンジニアは、Webサイトの情報を格納する「Webサーバー」や、メールの送受信を管理する「メールサーバー」など、さまざまな用途のサーバーの設計、構築、運用、保守を担当します。
具体的には、サーバー機器の選定やOS(Operating System)のインストール、各種設定作業などが主な仕事です。
特に、LinuxやWindows ServerといったサーバーOSに関する深い知識は不可欠です。
また、近年では物理的なサーバーを仮想的に分割して効率的に利用する「仮想化技術」(VMwareやHyper-Vなど)も必須スキルとなっています。
システムの安定稼働を維持するためのセキュリティ対策や、障害発生時の迅速な原因究明と復旧作業もサーバーエンジニアの重要な責務です。
アプリケーションが快適に動作するための土台を整える、まさにインフラの中核を担う専門職だと言えるでしょう。
ネットワークエンジニア
ネットワークエンジニアは、コンピューターやサーバー、スマートフォンなどを相互に接続し、データ通信を可能にする「ネットワーク」を専門に扱う技術者です。
ルーターやスイッチ、ファイアウォールといったネットワーク機器を駆使して、快適で安全な通信環境を設計、構築、運用します。
例えば、オフィス内のLAN(Local Area Network)環境の構築や、離れた拠点間を結ぶWAN(Wide Area Network)の設計といった仕事を担当します。
障害が発生すれば、社内システムやWebサービスが停止してしまうため、その責任は重大です。
そのため、ネットワーク機器の設定スキルはもちろん、TCP/IPといった通信プロトコルに関する深い理解が求められます。
近年では、物理的な構成に縛られず柔軟にネットワークを管理できるSDN(Software-Defined Networking)や、クラウド上のネットワーク構築に関する知識も重要性を増しています。
クラウドエンジニア
クラウドエンジニアは、Amazon Web Services (AWS)やMicrosoft Azure, Google Cloud (GCP) といったクラウドサービスを利用して、ITインフラを設計、構築、運用する専門家です。
従来のインフラエンジニアが物理的なサーバーやネットワーク機器を扱っていたのに対し、クラウドエンジニアは、クラウド事業者が提供するサービスを組み合わせてインフラを構築します。
この職種の最大の特徴は、物理的な制約から解放され、必要な時に必要な分だけリソースを迅速に確保できる点にあります。
そのため、ビジネスの成長に合わせて柔軟かつスピーディにシステムを拡張・縮小させることが可能です。
また、「Infrastructure as Code (IaC)」と呼ばれる、コードを用いてインフラ構成を自動で管理する技術が主流となっており、プログラミングや自動化のスキルも強く求められます。
現在、企業のクラウド利用は加速しており、クラウドエンジニアはインフラエンジニアの中でも特に需要が高く、将来性のある職種と言えるでしょう。
データベースエンジニア
データベースエンジニアは、企業の持つ膨大なデータを効率的に管理し、安全に活用するための「データベース」の設計、構築、運用、保守を専門としています。
顧客情報や商品データ、売上データなど、企業活動の根幹をなす情報を扱うため、非常に重要な役割を担います。
主な業務には、データベース管理システム(DBMS)であるOracle Database、MySQL、PostgreSQLなどのインストールや設定、そして最適なパフォーマンスを発揮できるようにデータベースを設計することが含まれます。
また、データのバックアップ計画の策定や、障害発生時にデータを復旧する手順の確立、不正なアクセスからデータを守るためのセキュリティ対策も重要な仕事です。
アプリケーションが必要なデータを迅速かつ正確に取り出せるように、SQLを用いてデータベースの性能を改善する「チューニング」もデータベースエンジニアの腕の見せ所でしょう。
インフラエンジニアの具体的な仕事内容

インフラエンジニアの仕事は、プロジェクトの開始からシステムの安定稼働を支えるまで、非常に多岐にわたります。
その業務は一般的に「上流工程」と「下流工程」に分けられます。
ここでは、一般的な業務の流れに沿って、具体的な仕事内容を5つのフェーズで見ていきましょう。
要件定義
要件定義は、プロジェクトの最も初期の段階であり、インフラ構築の方向性を決定する重要なフェーズです。
クライアントや自社のサービス企画担当者から、「どのようなシステムを作りたいのか」「どのような課題を解決したいのか」といった要望をヒアリングします。
この段階では、必要なサーバーの性能(CPU、メモリ、ディスク容量など)、想定されるアクセス数、システムの可用性(24時間365日稼働させる必要があるかなど)、セキュリティレベルといった、インフラに求められる条件を具体的に定義していきます。
予算や納期も考慮しながら、実現可能な仕様へと落とし込んでいく作業です。
技術的な知識だけでなく、相手の要求を正確に汲み取り、円滑に交渉を進めるコミュニケーション能力が不可欠な工程と言えるでしょう。
基本設計/詳細設計
要件定義で固まった内容をもとに、インフラの具体的な設計図を作成していきます。
この設計工程は、インフラの全体像を描く「基本設計」と、より具体的な設定値などを決める「詳細設計」の2段階に分かれています。
基本設計では、使用するサーバーやネットワーク機器の種類、OSやミドルウェアの選定、物理的な配置やネットワーク構成の骨子などを決定します。
一方、詳細設計では、サーバーのパラメータ設定値、IPアドレスの割り当て、ファイアウォールの通信ルールといった、構築作業に必要なレベルまで細かく仕様を詰めていく作業です。
ここで作成される「設計書」が、後の構築作業のすべてを規定する指示書となります。
将来的な拡張性や障害発生時の影響範囲なども考慮した、質の高い設計が求められるでしょう。
設計に基づいた構築作業
設計書が完成したら、次はいよいよインフラを実際に形にしていく「構築」のフェーズに移ります。
この工程では、設計書に記載された仕様に沿って、ハードウェアの設置やソフトウェアのインストール、各種設定を正確に行っていきます。
オンプレミス環境の場合は、データセンターなどでサーバーラックに機器を設置し、ケーブルを配線するといった物理的な作業も発生します。
その後、OSやミドルウェアのインストール、ネットワーク機器の設定などを行います。
クラウド環境の場合は、管理コンソール画面からの操作や、TerraformなどのIaCツールを用いてコードでインフラをプロビジョニングすることが主流です。
設計通りのインフラをミスなく作り上げる、正確性と着実さが求められる作業だと言えます。
インフラが問題なく稼働するかどうかのテスト
インフラの構築が完了したら、それが設計通りに正しく機能するか、そして要求された性能や品質を満たしているかを確認するための「テスト」を実施します。
このテスト工程を経ることで、サービスをリリースする前に問題点を洗い出し、システムの信頼性を担保することが可能になります。
テストには様々な種類があります。
例えば、個々の機器が正常に動くかを確認する「単体テスト」、システム全体が連携して動作するかを見る「結合テスト」、そして大量のアクセスを擬似的に発生させて高い負荷に耐えられるかを確認する「性能テスト(負荷テスト)」などです。
また、意図的に一部の機器を停止させ、バックアップシステムへ正常に切り替わるかを確認する「冗長化テスト」も重要です。
ここで発見された問題は、設計や構築のフェーズにフィードバックされ、修正が行われます。
運用・保守作業
システムが本番稼働を開始した後は、そのインフラが安定して動き続けるように維持管理する「運用・保守」のフェーズに入ります。
インフラエンジニアの業務において、この運用・保守が占める割合は非常に大きいものです。
運用業務には、システムが正常に稼働しているかを24時間365日監視する「死活監視」やリソース監視、定期的なバックアップの実行、セキュリティパッチの適用などが含まれます。
一方、保守業務は、システムに障害が発生した際の迅速な原因究明と復旧作業や、ハードウェアの故障対応、OSやミドルウェアのアップデート対応などを行います。
障害を未然に防ぎ、万が一発生した際にもサービスへの影響を最小限に食い止める、まさにITサービスの安定稼働を最前線で支える重要な仕事です。
現代のインフラエンジニアの仕事に必ず必要となる3大スキル

技術は絶えず進化しており、インフラエンジニアに求められるスキルセットも時代と共に変化しています。
現在、市場価値の高いインフラエンジニアとして活躍するために、特に重要となる3つのスキルセットを解説しますので、参考にしてください。
サーバーに関する知識・スキル
サーバーは、ITインフラストラクチャーの根幹をなす要素であり、その知識は依然としてインフラエンジニアにとって必須です。
特に、エンタープライズ環境で圧倒的なシェアを誇るLinuxと、Windows環境で標準的に利用されるWindows Serverという2大サーバーOSに関する深い理解が求められます。
コマンドライン操作やシェルスクリプティング、システム管理、セキュリティ設定など、OSを自在に扱えるスキルは基本中の基本です。
さらに、物理サーバーのリソースを仮想的に分割して効率的に利用する「仮想化技術」の知識も欠かせません。
VMware vSphereやKVM、Hyper-Vといった仮想化基盤の設計・構築・運用スキルは、オンプレミス環境だけでなく、クラウド技術を理解する上での土台にもなります。
ネットワークに関する知識・スキル
サーバーやクライアントPC、その他のデバイスを繋ぐネットワークがなければ、システムは機能しません。
そのため、ネットワークに関する知識・スキルもサーバーと同様に極めて重要です。
TCP/IPといった通信プロトコルの階層構造や仕組みを根本から理解していることは、トラブルシューティングの際に大きな力となるでしょう。
具体的には、ルーターやスイッチ、ファイアウォール、ロードバランサーといったネットワーク機器の役割を理解し、設定・運用できるスキルが求められます。
また、近年のトレンドとして、クラウドサービス上の仮想ネットワーク(AWSのVPCやAzureのVNetなど)を設計・構築するスキルや、ソフトウェアでネットワークを集中管理するSDN(Software-Defined Networking)の知識も、現代のインフラエンジニアにとって価値を高める要素となっています。
クラウドに関する知識・スキル
インフラエンジニアにとって最も重要性が増しているスキルが、クラウドに関する知識・スキルです。
多くの企業がインフラ基盤としてオンプレミスからクラウドへ移行、あるいは併用(ハイブリッドクラウド)しており、クラウドを扱えることはもはや必須条件となりつつあります。
特に、主要なクラウドプラットフォームであるAmazon Web Services (AWS)、Microsoft Azure、Google Cloud (GCP)のいずれか、あるいは複数に関する深い知識と実践経験が強く求められます。
具体的には、仮想サーバー、ストレージ、データベース、ネットワークといった各サービスを組み合わせて、要件に合ったインフラを設計・構築するスキルです。
さらに、TerraformやAnsibleといったツールを用いてインフラ構成をコードで管理する「Infrastructure as Code (IaC)」や、DockerやKubernetesといったコンテナ技術のスキルも、クラウドネイティブな開発が主流となる中で不可欠なものとなっています。
インフラエンジニアの仕事に役立つ資格
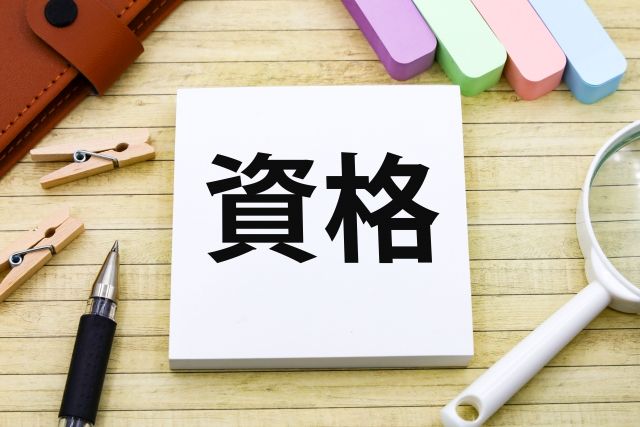
インフラエンジニアとしてのスキルや知識を客観的に証明し、キャリアアップや転職を有利に進める上で、資格の取得は非常に有効な手段です。
資格の勉強を通じて、体系的な知識を身につけることもできます。
インフラエンジニアの仕事に役立つ代表的な資格としては、主に以下のようなものがあります。
- ネットワークスペシャリスト試験
- データベーススペシャリスト試験
- LinuC
- LPIC
- CCNA
- AWS
インフラエンジニアを目指す際や、今もインフラエンジニアとして働いている場合に役立つ資格に関しては、以下の記事で詳しく解説しています。
インフラエンジニアの実務例

インフラエンジニアの仕事は多岐にわたりますが、具体的なプロジェクト例を見ることで、より業務内容をイメージしやすくなるでしょう。
ここでは、代表的な2つの実務例を紹介します。
ECサイトのインフラ構築プロジェクト
多くのユーザーが利用するECサイトでは、平常時の快適なレスポンスはもちろん、セール時などに発生する突発的なアクセス急増にも耐えられるインフラが求められます。
このような要件を満たすため、クラウド(ここではAWSを想定)を活用したプロジェクト例を見てみましょう。
| 要件定義・設計 | セール時のピークアクセス数を予測し、それに耐えうるサーバー構成やネットワーク帯域を定義します。負荷に応じてサーバー台数を自動で増減させる「オートスケーリング」や、アクセスを複数のサーバーに振り分ける「ロードバランサー(ELB)」の導入を設計に盛り込みます。データベースには、運用負荷が低いマネージドサービス「RDS」を選定します。 |
| 構築 | 設計に基づき、TerraformなどのIaCツールを用いてインフラをコード化し、自動で構築します。これにより、手作業によるミスを防ぎ、同じ環境を何度でも再現できるようになります。 |
| テスト | 構築後、負荷テストツールを用いて大量のアクセスを発生させ、レスポンスの遅延やエラーが発生しないか、オートスケーリングが正常に機能するかなどを徹底的に検証します。 |
| 運用 | リリース後は、CloudWatchなどの監視ツールでCPU使用率やネットワークトラフィックを常に監視し、異常の兆候があればアラートで即座に検知できる体制を整えます。 |
社内システムのオンプレミスからクラウドへの移行
コスト削減や運用効率化、災害対策などを目的に、企業が自社で保有・運用してきた「オンプレミス」環境のシステムを、クラウドへ移行するプロジェクトも増加しています。
ここでは、社内のファイルサーバーをAzureへ移行する例を考えてみましょう。
| 現状分析(アセスメント) | まず、既存のファイルサーバーの容量、利用状況、アクセスパターン、連携している他のシステムなどを詳細に調査します。 |
| 移行計画・設計 | 調査結果をもとに、Azureのどのサービス(Azure FilesやAzure NetApp Filesなど)が最適かを選定し、具体的な移行手順、スケジュール、移行後の運用体制などを計画・設計します。データ移行中のダウンタイムをいかに最小化するかが重要なポイントです。 |
| 移行作業 | 計画に基づき、Azure上に移行先の環境を構築します。その後、Azure Migrateなどの専用ツールや、Robocopyといったコマンドを利用して、オンプレミスからクラウドへデータを同期・転送します。 |
| 移行後テスト・切替 | データ移行が完了したら、アクセス権やファイルの内容が正しく移行されているかを検証します。問題がなければ、ユーザーのアクセス先をオンプレミスからAzureへと切り替え、移行を完了させます。 |
インフラエンジニアのキャリアパス

インフラエンジニアとして経験を積んだ後には、多様なキャリアパスが広がっています。
自身の適性や興味に応じて、専門性を深める道や、より上流の役割を目指す道、マネジメントへ進む道などを選択することが可能です。
スペシャリスト
特定の技術分野を極め、その領域の第一人者を目指すキャリアパスです。
高い専門性を武器に、複雑な課題解決や最新技術の導入をリードします。
| クラウドアーキテクト | クラウド技術に特化し、ビジネス要件に最適なクラウドインフラ全体を設計する専門家。 |
| セキュリティエンジニア | インフラのセキュリティに特化し、サイバー攻撃からシステムを守るための設計・実装・運用を行う専門家。 |
| SRE (Site Reliability Engineer) | Webサービスの信頼性向上をミッションとし、インフラの自動化やパフォーマンス改善、障害対応などを担当する専門家。 |
ジェネラリスト
サーバー、ネットワーク、クラウドなど、幅広い技術領域をカバーし、インフラ全体を俯瞰的な視点から最適化するキャリアパスです。
| ITアーキテクト | ビジネスと技術の両面を理解し、企業全体のIT戦略に基づいてシステム全体の構造を設計する上級職。 |
| フルスタックエンジニア | インフラだけでなく、アプリケーション開発にも精通し、開発から運用まで一気通貫で担当できるエンジニア。 |
マネジメント
技術力に加えて、チームやプロジェクト全体を管理する役割を担うキャリアパスです。
| プロジェクトマネージャー (PM) | プロジェクト全体の責任者として、予算、品質、納期(QCD)の管理を行い、プロジェクトを成功に導く。 |
| ITコンサルタント | 専門知識を活かして企業のIT戦略に関する課題を分析し、解決策を提案する。 |
まとめ
以上、インフラエンジニアの仕事内容について、その種類から具体的な業務の流れ、必要なスキル、キャリアパスに至るまで、詳しく解説しました。
インフラエンジニアは、ITシステムの基盤を支える、社会にとって不可欠な存在です。
さらに、「残業が少ない」「未経験からでも目指しやすい」「AIに仕事を奪われにくい」といった利点から、「インフラエンジニアは最強のエンジニア職」と言われることもあるほどです。
興味が湧いた方は、是非インフラエンジニアへの道にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!