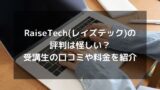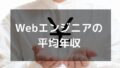クラウド技術の急速な普及により、クラウドエンジニアの需要は年々高まっています。
したがって、クラウドエンジニアを目指すため、もしくはクラウドエンジニアとしてさらに活躍するため、資格を取得しようと考えている人も多いでしょう。
しかし、「どの資格から取得すべきか」「本当に資格は必要なのか」と悩んでいる人もいるはずです。
そこでこの記事では、クラウドエンジニア向けのおすすめ資格を12個紹介します。
クラウドエンジニアに資格が必要かどうかや、資格取得のロードマップなどについても解説していきますので、是非参考にしてください。
 |
|

【スクール選びで後悔したくない方へ】
4年連続で人気No.1となっている「RUNTEQ」は、当ブログで調査した数多くのスクールの中でも大変おすすめです。なぜ選ばれ続けているのか、 その理由や受講生の評判については、以下の記事で詳しくまとめています。
※直接公式サイトを確認したい方はRUNTEQ公式サイトからどうぞ。
クラウドエンジニアに資格は必要?
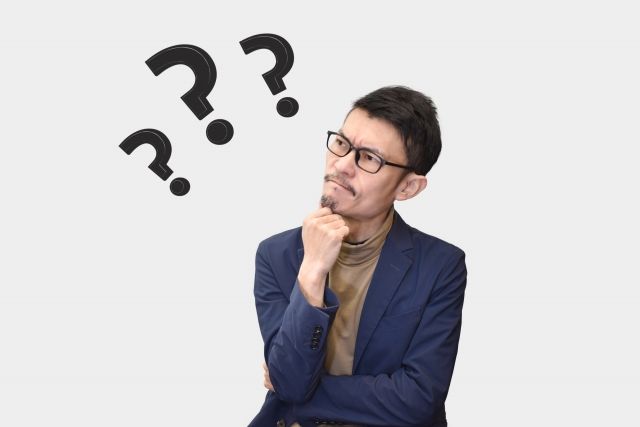
クラウドエンジニアとして活躍するために、資格の取得は必須ではありません。
しかし、資格を保有することで、専門知識やスキルを客観的に証明できるため、転職活動や昇進において大きなアドバンテージになるでしょう。
特に未経験からクラウドエンジニアを目指す場合、実務経験の不足を資格でカバーすることが可能です。
企業側も、資格保有者に対して一定の知識レベルを期待できるため、採用時の判断材料として重視する傾向があります。
また、資格取得の過程で体系的な知識を身につけられることも大きなメリットでしょう。
クラウドサービスは日々進化しており、最新の機能を学ぶ機会として資格学習は非常に有効です。
ただし、資格取得だけで満足するのではなく、ポートフォリオに磨きをかけてスキルアップすることも大事ですので忘れないでください。
クラウドエンジニアにおすすめの資格と難易度

クラウドエンジニアを目指す方にとって、どの資格から取得すべきか迷うことも多いでしょう。
ここでは、特に需要が高く、キャリアアップに直結する資格を厳選してご紹介します。
各資格の特徴や難易度を理解し、自身のスキルレベルや目標に合わせて選択してください。
AWS認定資格
AWS認定資格は、世界最大のクラウドプラットフォームであるAmazon Web Servicesの公式認定プログラムです。
基礎レベルの「Foundational(2種類)」から、「Associate(5種類)」、「Professional(2種類)」、「Specialty(3種類)」と、合計12種類の試験があります。
出題範囲は、EC2やS3などの基本サービスから、ネットワーキング、セキュリティ、コスト最適化まで幅広くカバーしています。
特にSolutions Architect Associateは、システム設計の観点からAWSサービスを総合的に理解する必要があるため、実務に直結する知識が身につくでしょう。
難易度について、合格率は非公開であるものの、Foundationalの合格率は約70%と言われています。
しかしProfessionalレベルになると、合格率は30%程度まで下がります。
Associateレベルの資格であれば、3〜6ヶ月程度の学習期間で合格を目指せるでしょう。
ただし、実際のAWS環境での操作経験がない場合は、ハンズオン学習を含めてもう少し時間がかかる可能性があります。
Google Cloud認定資格
Google Cloud認定資格は、Google Cloud Platform(GCP)の技術力を証明する資格体系です。Foundational(基礎)レベル、Associate(アソシエイト)レベル、そしてProfessional(プロフェッショナル)レベルの各種専門資格という3段階の構成になっています。
出題範囲として、Compute Engine、Cloud Storage、BigQueryなどの主要サービスに加え、機械学習系のサービスやKubernetesベースのGKEなども含まれます。
特にデータ分析やAI/MLに強みを持つGCPの特性を反映し、これらの分野の出題比重が高い傾向にあるでしょう。
難易度について、Cloud Digital Leaderは非技術者でも理解できる内容で、クラウドの基本概念やビジネス価値を問う問題が中心です。
Associate Cloud Engineerでは、実際のGCP環境でのタスク実行能力が求められ、コマンドラインやコンソールでの操作知識が必要になります。
Professionalレベルになると、複雑なアーキテクチャ設計やトラブルシューティング、最適化提案など、実務経験に基づいた判断力が試されるでしょう。
Microsoft Azure認定資格
Microsoft Azure認定資格は、企業向けクラウドサービスとして高いシェアを持つAzureの技術力を証明します。
AZ-900(Azure Fundamentals)から始まり、AZ-104(Azure Administrator)、AZ-305(Azure Solutions Architect Expert)など、役割別に体系化されているのが特徴です。
出題範囲は、仮想マシン、ストレージ、ネットワーキングといった基本的なIaaSサービスから、Azure Active DirectoryやMicrosoft 365との連携まで多岐にわたります。
特に企業のハイブリッドクラウド環境構築に関する問題が多く、オンプレミスとクラウドの統合に関する知識が求められるでしょう。
基礎レベルのAZ-900は合格率70%以上と言われているほど取得しやすい資格ですが、Expertレベルになると合格率は大きく下がります。
(合格率は非公開)
Azureは日本企業での採用率も高く、日本語の学習リソースも充実しているため、学習環境は整っていると言えるでしょう。
シスコ技術者認定(CCNA)
CCNAは、ネットワーク機器大手のシスコシステムズが提供する認定資格です。
クラウドエンジニアにとって、ネットワークの基礎知識は必須であり、CCNAはその土台を固めるのに最適な資格と言えるでしょう。
出題範囲は、TCP/IPプロトコル、ルーティング、スイッチング、ワイヤレス、セキュリティなど、ネットワーク全般をカバーしています。
2020年の改定により、SDN(Software-Defined Networking)やプログラマビリティなど、クラウド時代に対応した内容も追加されました。
合格率は25~30%程度で、ネットワーク初心者にとってはやや難易度が高いかもしれません。
しかし、クラウドサービスを利用する上で、VPCやサブネット設計、セキュリティグループの設定など、ネットワーク知識は欠かせません。
6ヶ月程度の学習期間を見込んで、じっくりと基礎を固めることをおすすめします。
実機での設定経験がない場合は、シミュレーターを活用した実践的な学習が効果的でしょう。
Linux技術者認定資格(LinuC)
LinuCは、日本のLPI-Japanが提供するLinux技術者認定資格です。
クラウド環境の多くがLinuxベースで動作しているため、Linuxの知識はクラウドエンジニアにとって必須のスキルと言えるでしょう。
出題範囲は、レベル1では基本的なコマンド操作やファイルシステム、プロセス管理など、レベル2ではネットワーク設定やセキュリティ、仮想化技術などが含まれます。
2020年のバージョン10.0への改定により、コンテナ技術やクラウドセキュリティなど、最新のトレンドを反映した内容になりました。
レベル3は、専門分野別に「Mixed Environment」「Security」「Virtualization & High Availability」の3つの認定に分かれています。
Mixed Environmentでは異種システム間の連携、SecurityではLinuxシステムのセキュリティ強化、Virtualization & High Availabilityでは仮想化技術と高可用性システムの構築が主な出題範囲となります。
難易度は、レベルが上がるほど難しくなります。
それぞれのレベルに合格するために必要な勉強時間の目安は以下の通りです。
- レベル1:1~3か月程度
- レベル2:3~6か月程度
- レベル3:6か月~1年程度
VMware認定資格
VMware認定資格は、仮想化技術のリーディングカンパニーであるVMwareの製品知識を証明します。
多くの企業がオンプレミスからクラウドへの移行過程にあり、VMwareの仮想化技術は重要な役割を果たしています。
VCP(VMware Certified Professional)では、vSphereの基本操作から高可用性構成、リソース管理まで幅広く出題されます。
特にvMotionやDRSなどの独自機能に関する深い理解が求められるでしょう。
また、VMware Cloud on AWSなど、パブリッククラウドとの連携に関する内容も含まれています。
合格率は公表されていませんが、実務経験なしでの合格は困難とされています。
必須となる公式トレーニングの受講も含めると、準備期間は最低でも3ヶ月は必要でしょう。
CCSP
CCSP(Certified Cloud Security Professional)は、(ISC)²が提供するクラウドセキュリティに特化した国際認定資格です。
クラウド環境におけるセキュリティの重要性が高まる中、CCSPは高度な専門性を証明する資格として注目されています。
出題範囲は、クラウドのコンセプトとアーキテクチャ、ガバナンス、プラットフォームセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、運用など6つのドメインで構成されています。
特定のクラウドプラットフォームに依存しない、ベンダーニュートラルな内容であることが特徴でしょう。
合格率は公表されていませんが、5年以上のIT実務経験(うち3年はセキュリティ、1年はクラウド)が受験要件となっていることから、かなり難易度が高いと予想されます。
CompTIA認定資格
CompTIA認定資格は、ベンダーニュートラルなIT認定として世界的に認知されています。
クラウドエンジニアには、Cloud+やSecurity+、Network+などが特に有用でしょう。
Cloud+は、複数のクラウドプラットフォームに共通する概念や技術を学べます。
出題範囲は、クラウドアーキテクチャ、セキュリティ、デプロイメント、運用、トラブルシューティングなど実践的な内容が中心です。
特定のベンダーに偏らない知識を身につけられるため、マルチクラウド環境で働く際に役立つでしょう。
合格率は発表されていませんが、約50%ほどと言われています。
IT経験2〜3年程度の方を対象としており、日本語での受験も可能で、学習教材も比較的充実しています。
ベンダー資格と比べて知名度は劣るかもしれませんが、基礎力を証明する資格として、初学者にもおすすめできます。
ネットワークスペシャリスト試験
ネットワークスペシャリスト試験は、情報処理推進機構(IPA)が実施する国家資格です。
高度IT人材として、ネットワークシステムの企画・要件定義・開発・運用・保守において中心的な役割を果たすことが期待されています。
出題範囲は、ネットワーク技術全般に加え、セキュリティ、信頼性設計、性能設計など幅広い知識が求められます。
特に午後試験では、実際の業務シナリオに基づいた記述式問題が出題され、深い理解と応用力が試されるでしょう。クラウドネットワークに関する出題も年々増加しています。
合格率は例年15%前後と、情報処理技術者試験の中でも特に難易度が高い試験です。
ネットワークの実務経験がない場合、1年以上の学習期間が必要になることも珍しくありません。
しかし、国家資格としての信頼性は高く、大手企業や官公庁での評価も高いため、学習時間を割いてでも取得する価値はあるでしょう。
情報処理安全確保支援士試験
情報処理安全確保支援士試験(通称:登録セキスペ)は、サイバーセキュリティに関する国家資格です。
クラウド環境のセキュリティ対策は重要な課題であり、この資格はセキュリティ専門家としての能力を証明します。
出題範囲は、情報セキュリティマネジメント、ネットワークセキュリティ、アプリケーションセキュリティ、セキュリティ監査など多岐にわたります。
近年では、クラウドセキュリティやゼロトラストアーキテクチャに関する出題も増えています。記述式問題では、実際のインシデント対応や対策立案能力が問われるでしょう。
合格率は約20%程度で、高度な専門知識と実践的な思考力が必要です。
合格後は登録制となり、継続的な講習受講が義務付けられています。
この制度により、常に最新のセキュリティ知識を維持できることが特徴でしょう。
基本情報技術者試験
基本情報技術者試験は、ITエンジニアの登竜門とも言える国家資格です。
クラウドエンジニアを目指す初学者にとって、IT全般の基礎知識を体系的に学べる良い機会となるでしょう。
出題範囲は、コンピュータシステム、データベース、ネットワーク、セキュリティ、プログラミング、プロジェクトマネジメントなど、ITに関する幅広い分野をカバーしています。
2023年4月からCBT方式に移行し、年間を通じて受験可能になりました。
科目A(旧午前)と科目B(旧午後)の2部構成で、特に科目Bではアルゴリズムとプログラミングの問題が重視されています。
合格率は約40〜50%で、IT未経験者でも3〜6ヶ月程度の学習で合格を目指せます。
直接的にクラウド技術を扱う試験ではありませんが、クラウドサービスを理解する上で必要な基礎知識を網羅的に学べることがメリットでしょう。
応用情報技術者試験
応用情報技術者試験は、基本情報技術者試験の上位に位置する国家資格です。
より高度なIT知識と、それを実務に応用する能力が求められます。
クラウドエンジニアとして、アーキテクチャ設計やプロジェクト管理に携わる際に必要な知識が身につくでしょう。
出題範囲は基本情報と重複する部分もありますが、より深い理解と応用力が必要です。
特に午後試験では、システム設計、プログラミング、プロジェクトマネジメントなどから選択して解答する形式で、自身の得意分野を活かせます。
近年では、クラウドコンピューティングやIoT、AIなど最新技術に関する出題も増えています。
合格率は約25%程度で、基本情報と比べて難易度は大幅に上がります。
実務経験がない場合、6ヶ月〜1年程度の学習期間を見込む必要があるでしょう。
クラウドエンジニアが資格を取得するメリット

クラウドエンジニアにとって資格取得は、単なる知識の証明以上の価値をもたらします。
キャリア形成や実務能力の向上において、資格がどのような役割を果たすのか、具体的なメリットを3つの観点から解説します。
クラウドエンジニアとしてのスキルを客観的に証明できる
資格取得の最大のメリットは、自身のスキルレベルを第三者に対して客観的に証明できることです。
特に転職市場において、実務経験が浅い場合でも、資格保有により一定の知識水準を満たしていることをアピールできるでしょう。
企業の採用担当者にとって、応募者のスキルを正確に評価することは困難な作業です。
しかし、AWS認定ソリューションアーキテクトやGoogle Cloud Professional Cloud Architectなどの資格を保有していれば、少なくともクラウドに関して一定の知識を持っていることが保証されます。
体系的に学習できるので知識の抜け漏れがなくなる
実務経験だけでは、担当プロジェクトで使用する機能やサービスに知識が偏りがちです。
資格学習を通じて、普段触れる機会の少ない領域も含めて網羅的に学習できることは、エンジニアとしての成長に大きく貢献します。
例えば、EC2やS3などの基本的なサービスは日常的に使用していても、AWS Organizationsによる複数アカウント管理やAWS CloudFormationによるインフラのコード化など、上級機能については理解が不十分なケースがあるでしょう。
資格試験では、これらの機能も出題範囲に含まれるため、強制的に学習する機会が生まれます。
年収が上がる可能性がある
多くの企業では、資格手当制度を設けており、資格取得が直接的な収入アップにつながることがあります。
特にクラウド関連資格は、企業のDX推進において重要視されているため、月額1〜5万円程度の手当が支給されるケースも珍しくありません。
また、資格取得は昇進や昇格の判断材料としても活用されています。
上級エンジニアやアーキテクト、マネージャーへの昇進条件として、特定の資格保有を求める企業も増えているでしょう。
長期的なキャリア形成を考えると、クラウドエンジニアとして年収を上げるためには、資格取得には一定の効果があると言えます。
クラウドエンジニアが取得する資格を選ぶ際のポイント

数多くあるクラウド関連資格の中から、自分に最適な資格を選ぶことは容易ではありません。
効果的なキャリア形成のために、どのような観点で資格を選択すべきか、3つの重要なポイントを解説します。
自分のスキルにあった難易度の資格から受験する
資格取得において最も重要なのは、現在の自分のスキルレベルに適した資格から始めることです。
いきなり高難度の資格に挑戦して挫折するよりも、段階的にステップアップしていく方が、着実にスキルを身につけられるでしょう。
クラウド未経験者であれば、AWS Cloud PractitionerやGoogle Cloud Digital Leaderなどの基礎レベルから始めることをおすすめします。
これらの資格は、クラウドの基本概念やサービスの概要を学ぶのに最適で、合格率も比較的高いため、モチベーション維持にも効果的です。
将来的なキャリアを考慮して選ぶ
資格を選択する際は、5年後、10年後の自分のキャリアを明確にイメージすることが重要です。
クラウドアーキテクトを目指すのか、セキュリティスペシャリストになりたいのか、それともデータエンジニアとして活躍したいのかによって、取得すべき資格は大きく異なります。
例えば、インフラ設計に特化したキャリアを歩みたい場合は、各クラウドベンダーのアーキテクト系資格を中心に取得していくべきでしょう。
一方、セキュリティ分野でのキャリアを考えている場合は、CCSPや情報処理安全確保支援士などのセキュリティ専門資格が有効です。
自身の興味関心と市場の需要を照らし合わせながら、戦略的に資格を選択することが重要です。
取得する価値がある資格か考える
すべての資格が同じ価値を持つわけではありません。
時間と費用を投資する前に、その資格が本当に自分のキャリアに有益かどうかを慎重に検討する必要があります。
まず確認すべきは、その資格の市場での認知度と需要です。
求人サイトで資格名を検索し、どれだけの企業が求めているかを調べてみましょう。
また、技術の陳腐化リスクも考慮すべきでしょう。
クラウド技術は日進月歩で進化しているため、数年後には価値が薄れる可能性のある資格もあります。
学習時間を投下するわけですから、投資対効果を冷静に分析し、本当に価値のある資格に絞って挑戦することが、効率的なキャリア形成につながるでしょう。
クラウドエンジニア向け資格を取得するための学習ロードマップ

資格取得を成功させるためには、計画的な学習が不可欠です。
ここでは、効率的に合格を目指すための具体的なロードマップを4つのステップに分けて解説します。
自分に必要な資格を選別する
学習を始める前に、まず自分のキャリアのゴールと現在のスキルレベルを客観的に評価することが重要です。
職務経歴書を見直し、これまでの経験で習得したスキルと、今後身につけるべきスキルのギャップを明確にしましょう。
次に、所属企業や転職市場で求められている資格をリサーチします。
社内の評価制度で優遇される資格や、目指すポジションの求人で頻繁に要求される資格を優先的に選択することで、資格取得の効果を最大化できるでしょう。
また、学習に必要な時間と予算も考慮する必要があります。
仕事や家庭との両立を考えながら、現実的に達成可能な目標を設定することが、挫折を防ぐ重要なポイントです。
複数の資格を検討している場合は、優先順位をつけて段階的に取得していく計画を立てましょう。
資格取得に向けての学習方法を決める
効果的な学習方法は、個人の学習スタイルや生活環境によって異なります。
- 独学
- メンターを探す
- プログラミングスクール
どの方法が向いているかは人によるでしょう。
また、独学を選んだとしても、「どのように独学を進めるか」という学習方法を決めなければなりません。
例えばオンライン学習サイトを利用するのか、書籍メインで学ぶのか、YouTubeで資格専門チャンネルを探すのか、もしくはこれらのハイブリッド型なのか。
このように、学習の進め方を決めることも大事です。
なお学習サイトを利用する場合は、ドットインストールやProgateといったサイトが便利でしょう。
合格に必要な学習を行なう
本格的な学習段階では、試験範囲を網羅的にカバーすることが重要です。
まずは試験ガイドを熟読し、出題される各ドメインの比重を把握しましょう。
重要度の高い分野から優先的に学習することで、効率的に得点力を向上させられます。
理論学習と実践学習のバランスも大切です。
特にトラブルシューティングやベストプラクティスに関する問題は、実務経験がないと解答が難しいため、様々なシナリオを想定して練習することが必要です。
過去問や模擬テストを探す
試験対策の最終段階では、実際の試験形式に慣れることが重要です。
公式の模擬試験は必ず受験し、出題形式や時間配分を体験しておきましょう。
多くの認定資格では、本番と同じ形式の練習問題が提供されています。
市販の問題集やオンラインの模擬試験サービスも活用しましょう。
ただし、非公式の教材については、内容の正確性を慎重に判断する必要があります。
古い情報や誤った解説が含まれている場合もあるため、複数の情報源を参照して確認することをおすすめします。
模擬試験で間違えた問題は、必ず復習して理解を深めましょう。
単に正解を暗記するのではなく、なぜその答えが正しいのかを説明できるレベルまで理解することが重要です。
クラウドエンジニアの資格取得におすすめのプログラミングスクール

独学での資格取得が困難な場合や、より効率的に学習したい場合は、プログラミングスクールの活用も有効です。
ここでは、クラウド資格取得に定評のある3つのスクールを紹介します。
RaiseTech
RaiseTechは、現役エンジニアによる実践的な指導が特徴のオンラインスクールです。
AWS認定資格の取得を目指すコースでは、単なる試験対策だけでなく、実務で使える知識とスキルの習得に重点を置いています。
カリキュラムは、AWS Solutions Architect Associateの取得を目標に設計されており、EC2、VPC、S3などの基本サービスから、CloudFormationによるインフラ自動化まで幅広くカバーしています。
週2回のライブ授業に加え、質問し放題のサポート体制が整っているため、疑問点をすぐに解決できるでしょう。
テックアカデミー
テックアカデミーは、豊富なコースラインナップと柔軟な学習スタイルで人気のオンラインスクールです。
クラウドエンジニアコースでは、AWS認定資格の取得に加えて、実際のWebアプリケーション開発も経験できます。
メンター制度が充実しており、週2回のマンツーマンメンタリングで個別の質問や相談に対応してもらえます。
また、毎日15時から23時まではチャットサポートも利用可能なため、仕事終わりの学習でも安心して取り組めるでしょう。
インターネット・アカデミー
インターネット・アカデミーは、25年以上の教育実績を持つ老舗のIT専門スクールです。
クラウドエンジニア育成コースでは、AWS、Azure、GCPの主要3プラットフォームを横断的に学習できることが特徴です。
通学とオンラインのハイブリッド形式で受講でき、ライフスタイルに合わせて学習方法を選択できます。
教育訓練給付金制度の対象コースもあるため、費用面でのハードルも低いでしょう。
まとめ
以上、クラウドエンジニアを目指す人や、すでにクラウドエンジニアとして働いている人が取得することで役立つ資格や、資格取得のためのロードマップなどについて詳しく解説してきました。
クラウド技術は今後もますます重要性を増していくはずです。
そんな状況だからこそ、資格取得に挑戦し、クラウド時代をリードするエンジニアとして自分の価値を高めておくのもよいでしょう。

【スクール選びで後悔したくない方へ】
4年連続で人気No.1となっている「RUNTEQ」は、当ブログで調査した数多くのスクールの中でも大変おすすめです。なぜ選ばれ続けているのか、 その理由や受講生の評判については、以下の記事で詳しくまとめています。
※直接公式サイトを確認したい方はRUNTEQ公式サイトからどうぞ。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!