ネットワークエンジニアを目指す多くの方が、登竜門として「CCNA」の取得を検討します。
しかし「CCNAは難しすぎる」「勉強を始めたが挫折しそう」といった声も少なくありません。
CCNAは、世界最大のネットワーク機器メーカーであるシスコシステムズ社が認定する資格であり、その内容は確かに専門的です。
この記事では、なぜCCNAが「難しすぎる」と感じられるのか、その理由と実際の難易度、合格率の目安、合格するための具体的な勉強方法などについて詳しく解説していきますので、是非参考にしてください。
 |
|

【スクール選びで後悔したくない方へ】
4年連続で人気No.1となっている「RUNTEQ」は、当ブログで調査した数多くのスクールの中でも大変おすすめです。なぜ選ばれ続けているのか、 その理由や受講生の評判については、以下の記事で詳しくまとめています。
※直接公式サイトを確認したい方はRUNTEQ公式サイトからどうぞ。
CCNAは難しすぎるのか?

結論から言えば、CCNAはIT未経験の初心者にとって「決して簡単ではないが、正しい手順で学習すれば十分に合格可能な資格」です。
CCNAが「難しすぎる」と感じられるのは、IT系資格の中でも特に実践的な知識と操作スキルが問われるためでしょう。
例えば、他のIT系資格と比較すると、ITパスポートや基本情報技術者試験がITに関する広範な「知識」を問う試験であるのに対し、CCNAはネットワークという特定分野の「深い理解」と「実機操作」を求めます。
- ネットワークの仕組み
- IPアドレスの割り当て
- ルーターやスイッチといった専門機器の設定方法
このように、日常生活では触れることのない概念をゼロから学ぶ必要があるのです。
2020年2月に試験制度が改定されて現在の試験(200-301)になりましたが、従来のルーティング&スイッチング分野だけでなく、セキュリティ、自動化といった現代のネットワーク技術に必須の分野までカバーしなければならなくなりました。
試験範囲が広くなったことも、難易度が高いと感じさせる一因かもしれません。
しかし、裏を返せば、CCNAに合格することは、現代のネットワークエンジニアに求められる広範な基礎知識とスキルを有していることの強力な証明となります。
難易度が高いからこそ、取得した際の価値も高い資格なのです。
CCNAが難しいと言われる理由
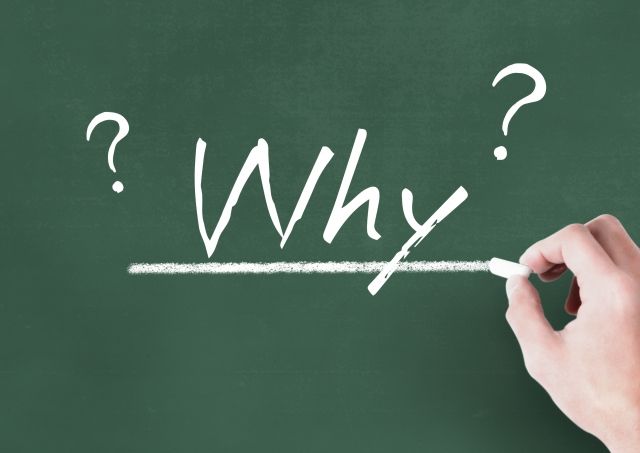
初心者にとって、CCNAが「難しすぎる」と感じられるのには、いくつかの理由が存在します。
学習を始める前に、どのような点が壁になるのかを把握しておくことが重要です。
試験範囲が幅広い
現在のCCNA(200-301)は、特定の分野に特化していた旧試験を統合し、ネットワークエンジニアの基礎を網羅する内容へと変更されました。
具体的には、以下の6つの主要な分野から出題されます。
- ネットワークの基礎(TCP/IPモデル、物理層、IPアドレッシングなど)
- ネットワークアクセス(VLAN、スイッチング、Wi-Fiなど)
- IPコネクティビティ(ルーティングの仕組み、OSPFなど)
- IPサービス(NAT、DHCP、DNSなど)
- セキュリティの基礎(VPN、ACL、WPA3など)
- 自動化とプログラマビリティ(Python、JSON、APIの概念など)
このように、従来の中心であったルーターやスイッチの設定知識に加え、セキュリティやプログラミングの基礎まで含まれています。
IT未経験者にとっては、これらすべてを同時に学ぶ必要があるため、学習すべき内容が膨大に感じられるでしょう。
初心者にとっては馴染みのない専門用語が多い
ネットワークの世界は、専門用語の宝庫です。
「ルーター」「スイッチ」といった機器の名前はもちろん、「OSI参照モデル」「カプセル化」「TCP/IP」「VLAN」「サブネットマスク」「DHCP」「DNS」「ACL」など、IT業界未経験者にとっては外国語のように聞こえるかもしれません。
CCNAの学習は、まずこれらの用語が「何を指していて」「どのような役割を果たしているのか」を正確に暗記し、理解することから始まります。
例えば、データが送信される際に各層(レイヤー)で情報が付加されていく「カプセル化」のプロセスや、IPアドレスの枯渇対策である「NAT」の仕組みなどは、単語だけ覚えても問題は解けません。
それぞれの技術がなぜ必要なのか、互いにどう連携しているのかを関連付けて理解する必要があり、その複雑さが初心者の学習を阻む壁となりがちです。
シミュレーション問題の難易度が高い
CCNAが他の多くのIT資格と一線を画す最大の理由が、「シミュレーション問題」の存在です。
シミュレーション問題は、単なる知識を問う選択問題とは異なり、試験画面上に表示される仮想のルーターやスイッチに対し、受験者自身がコマンド(Cisco IOS)を打ち込んで設定を行う実技問題です。
例えば、「特定のネットワーク間で通信できるようにルーティング設定を行ってください」「セキュリティ向上のため、このスイッチにVLANを設定してください」といった指示が出されます。
参考書を読んだだけでは、これらのコマンドを正しく実行することは不可能です。
Ciscoが無料で提供している「Packet Tracer(パケットトレーサー)」などのシミュレータソフトを使い、日頃から実際に手を動かしてネットワーク機器の設定演習を積んでいなければ、まず太刀打ちできません。
この「実機操作」のスキルが求められる点が、CCNAの難易度を格段に引き上げています。
問題数に対して試験時間が短い
CCNAの試験時間は120分ですが、出題される問題数は約100問です。
単純計算で、1問あたりにかけられる時間は約1分12秒しかありません。
すぐに解答できる知識問題もありますが、前述のシミュレーション問題や、IPアドレスの範囲を計算する「サブネット計算」問題は、1問解くのに数分を要することもあります。
さらに、CCNAの試験システムは、一度解答して次の問題に進むと、前の問題に戻って見直すことができない仕様になっています。
時間的なプレッシャーの中で、専門用語を理解し、計算問題をこなし、シミュレーション操作まで行う必要があるため、知識があやふやな状態では時間が全く足りなくなるでしょう。
CCNAの合格率や合格ライン

CCNAの難易度を客観的に測る指標として、合格率や合格ラインが気になるところです。
まず前提として、シスコシステムズ社は、CCNAの「合格率」および「正確な合格ライン(合格点)」を公式には一切公表していません。
合格ラインについては、試験の統計データに基づき変動するとされています。
しかし、一般的には1000点満点中、825点から850点程度が合格の目安であると言われています。
この合格ラインは、他の資格試験と比較すると非常に高い得点率でしょう。
合格率に関しても公式な発表はありませんが、学習サイトやITスクールの情報によれば、独学での初回合格率は20%〜30%程度ではないかと推測されています。
これは、前述したような試験範囲の広さやシミュレーション問題の存在により、十分な対策ができていないまま受験する人が多いためと考えられます。
非公式の数値とはいえ、合格に必要な点数が高く、合格率も低めであることから、CCNAが「難しすぎる」と感じる人が一定数いるのは当然のことでしょう。
難しすぎると言われるCCNAに合格するメリット・デメリット
シスコシステムズの認定資格の中ではアソシエイトレベル(5段階中、下から2番目)に属するCCNAですが、初心者にとっては難しすぎると感じることも少なくありません。
そんなCCNAですが、苦労して取得する価値はあるのでしょうか?
この項目では、CCNAを取得するメリットとデメリットについて解説していきます。
CCNAに合格するメリット

CCNAを取得するメリットは非常に大きく、特にネットワークエンジニアとしてのキャリアを目指す上では欠かせないものとなっています。
主なメリットは以下の通りです。
CCNAの学習を通じて、ネットワークの基礎からセキュリティ、自動化まで、現代のエンジニアに必要な知識を体系的に学ぶことができます。合格することで、それらの知識を確実に保有していることの客観的な証明となります。
ネットワーク機器の分野においてシスコシステムズ社は圧倒的なシェアを誇ります。そのため、同社の認定資格であるCCNAは、日本国内のみならず世界中で通用する「業界標準のパスポート」として高い認知度を持っています。
インフラ系エンジニア、特にネットワークエンジニアの求人募集では、「CCNA取得者優遇」や「CCNA保有必須」としている企業が数多く存在します。未経験からでも、CCNAを保有しているだけで、ITインフラへの強い関心と基礎知識をアピールでき、選考で非常に有利に働きます。
企業によっては、CCNA取得者に対して資格手当を支給する制度があります。また、CCNAはあくまでエントリーレベルの資格であり、より上位のCCNP(プロフェッショナル)やCCIE(エキスパート)といった資格への第一歩です。キャリアアップとそれに伴う年収向上を目指す上での基盤となります。
CCNAに合格するデメリット

一方で、CCNAを目指す上でのデメリットや注意点も存在します。
CCNAの受験料は300ドル(税別)です。日本円に換算すると、為替レートにもよりますが「45,000円以上」となり、資格試験としては高額な部類です。「難しすぎる」と感じて準備不足のまま受験し、不合格となると、再受験の経済的負担は大きなものになります。
CCNA認定は、取得日から3年間のみ有効です。資格を維持し続けるためには、3年以内に「再認定試験に合格する」か、「上位資格(CCNPなど)に合格する」、あるいは「シスコの継続教育(CE)プログラムで所定のクレジットを取得する」必要があります。IT技術の進歩は速いため、知識を常に最新の状態に保つ努力が求められます。
CCNAの試験範囲や出題形式

CCNAが「難しすぎる」と感じる一因である広範な試験範囲について、現在の「200-301 CCNA」試験で問われる内容と、その出題形式を正確に把握しておきましょう。
試験範囲は、以下の6つの分野で構成されており、それぞれ出題比率が定められています。
| 分野 | 出題比率 | 主な内容 |
|---|---|---|
| 1. ネットワークの基礎 | 20% | ルーター、スイッチ、TCP/IPモデル、IPアドレッシング、サブネット計算など |
| 2. ネットワークアクセス | 20% | VLAN、トランキング(802.1q)、EtherChannel、Wi-Fi(WLC)など |
| 3. IP接続 | 25% | ルーティングの仕組み(ルーティングテーブル)、静的ルーティング、OSPFv2など |
| 4. IPサービス | 10% | NAT(静的、動的、PAT)、DHCP、DNS、SNMP、FTP/TFTPなど |
| 5. セキュリティ基礎 | 15% | VPN、アクセス制御リスト(ACL)、ポートセキュリティ、WPA3など |
| 6. 自動化とプログラマビリティ | 10% | Pythonの基礎、JSON、REST API、SDN(Software-Defined Networking)の概念など |
特筆すべきは「自動化とプログラマビリティ」が10%含まれている点です。
ネットワーク運用を自動化する現代的なスキルも問われるようになり、従来のネットワーク知識だけでは合格できなくなっています。
出題形式は、主に以下のものが組み合わされます。
- 多肢選択問題
- ドラッグ&ドロップ問題
- シミュレーション問題
CCNA合格に必要な勉強時間
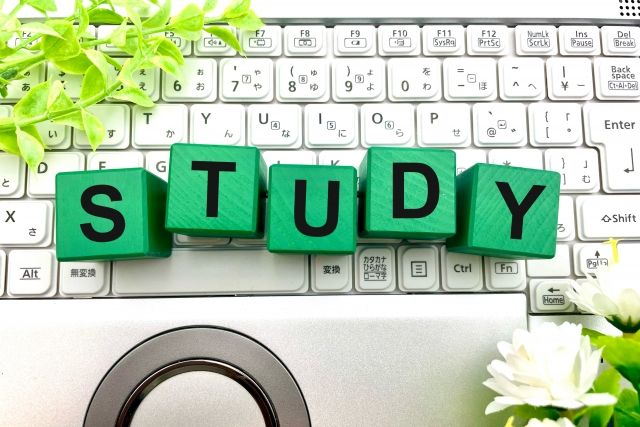
CCNA合格に必要な勉強時間は、受験者の現在の知識や経験によって大きく変動します。
まず、IT未経験・ネットワーク知識ゼロの場合は最も時間がかかり、一般的に「150時間〜200時間」程度が目安とされています。
1日2時間の勉強を継続しても、約3ヶ月から4ヶ月は必要になる計算です。
専門用語の暗記、サブネット計算の習熟、そしてシミュレータ操作の練習に多くの時間を割く必要があります。
ITパスポートや基本情報技術者試験に合格しているような、ITの基礎知識がある人の場合は、ネットワーク以外の基礎が身についているため、学習はスムーズに進むでしょう。
「100時間〜150時間」程度が目安となります。
ただし、サブネット計算や実機操作は別途集中的な学習が必要です。
ネットワーク運用・保守といった実務経験が場合は、知識の再確認とCCNA特有の出題範囲(特に自動化など)のキャッチアップが中心となります。
「50時間〜80時間」程度でも合格圏内に入ることが可能です。
重要なのは、総時間数よりも「シミュレータ演習にどれだけ時間をかけたか」です。
参考書を読むだけのインプット学習に偏ると、時間ばかりかかってシミュレーション問題に対応できません。
CCNAが「難しすぎる」と感じた時におすすめの勉強方法
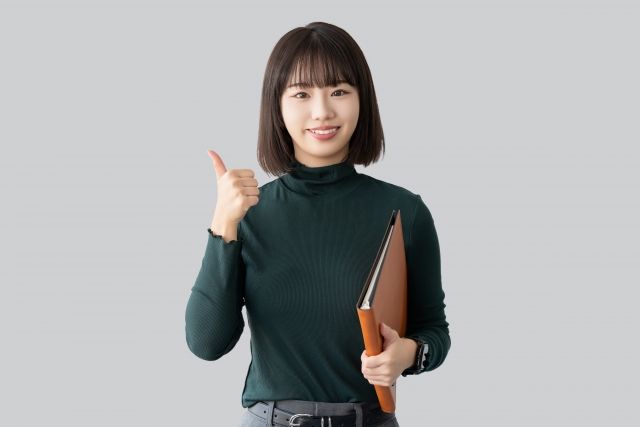
CCNAの広範な試験範囲と専門性に圧倒され、「難しすぎる」「受かる気がしない」と感じることは珍しくありません。
そのような壁に直面した際に有効な、具体的な学習戦略を紹介します。
試験範囲を分割して段階的に学習する
CCNAの6つの分野を一度に学ぼうとすると、情報量が多すぎて混乱してしまいます。
まずは試験範囲を分野ごとに分け、一つひとつ確実にクリアしていくような形で勉強を進めましょう。
具体的には以下の通りです。
-
「ネットワークの基礎」を最優先で学びます。OSI参照モデル、TCP/IP、そして最難関とも言われる「サブネット計算」は、この段階で徹底的にマスターしてください。
-
次に「ネットワークアクセス」(VLANやスイッチング)と「IPコネクティビティ」(ルーティング)に進みます。
-
基礎が固まったら、「IPサービス」「セキュリティの基礎」といった応用分野に進みます。
-
最後に、毛色の異なる「自動化とプログラマビリティ」を学びます。
このように段階を踏むことで、各技術の関連性が見えやすくなり、知識が定着しやすくなります。
模擬問題を繰り返し解く
参考書を一通り読み終え、一旦インプットが終わったという段階でも、模擬試験を解くと半分も正解できないでしょう。
CCNAの試験は、知識として「知っている」ことと、問題を「解ける」ことが直結しないためです。
そこで、「Ping-t」のような有名な学習サイトや、参考書に付属する模擬試験、シスコが提供する「Packet Tracer」という無料のシミュレータを徹底的に活用してください。
特にシミュレーション問題対策として、Packet Tracer上で「VLANを構築する」「ACLを設定する」「OSPFでルーティングする」といった基本的なネットワーク構成を、何も見ずにコマンドで組めるようになるまで繰り返し練習することが、合格への最短距離となります。
CCNAに強いスクールを活用する
独学での挫折経験がある方や、「難しすぎる」と感じて学習が停滞している方には、プログラミングスクールの活用が非常に有効な手段となります。
スクールを利用するメリットは、以下の点にあります。
- 現役エンジニアの講師から直接、ネットワークに関する難解な概念をわかりやすく教えてもらえる。
- シミュレータ演習だけでなく、実機に触れる環境が提供される場合がある。
- 体系化されたカリキュラムに沿って進めるため、学習の抜け漏れが防げる。
- 同じ目標を持つ仲間と学ぶことで、モチベーションを維持しやすい。
- 資格取得後の就職・転職サポートまで一貫して受けられる。
プログラミングスクールの中でも、特に「ウズウズカレッジ」と「ネットビジョンアカデミー
![]() 」がCCNA対策に力を入れているので、興味のある方は一度無料相談に申し込んでみるとよいでしょう。
」がCCNA対策に力を入れているので、興味のある方は一度無料相談に申し込んでみるとよいでしょう。
「CCNAは難しすぎる」と感じている人によくある質問

最後に、CCNAの難易度に関して初心者が抱きがちな疑問について、Q&A形式で回答します。
受かる気がしないけど、本当に初心者でも合格できる?
合格できます。
現在ネットワークエンジニアとして活躍している多くの専門家も、最初は同じように「OSI参照モデルとは何か」という地点からスタートしています。
CCNAが難しく感じるのは、学習内容が日常とかけ離れているだけで、内容自体が極端に高度というわけではありません。
正しい学習教材を選び、特にPacket Tracerを使ったシミュレータ演習に十分な時間をかければ、未経験者でも必ず合格ラインに到達可能です。
CCNAの過去問は公開されている?
いいえ、公開されていません。
シスコシステムズ社は、受験者に試験内容に関する秘密保持契約(NDA)への同意を求めています。
そのため、試験問題そのもの(過去問)をインターネット上で公開したり、共有したりする行為は契約違反となります。
公式ガイドや信頼できる参考書、Ping-tのような実績のある学習サイト、Packet Tracerを使って、正当な実力を身につけてください。
英語ができないとCCNAの合格は厳しい?
厳しくありません。
CCNA(200-301)試験は、日本語で受験することが可能です。
試験問題、選択肢、シミュレーションの指示など、すべて日本語で表示されます。
ただし、シミュレーション問題で入力するコマンド(例: show ip route や configure terminal)は英語です。
また、ネットワークの世界では技術文書やエラーメッセージの多くが英語であるため、将来的にエンジニアとしてキャリアアップしていく上では、英語に慣れておいた方が有利であることは間違いありません。
しかし、「受験合格」だけを考えれば英語力は不要です。
CCNAに有効期限はある?
はい、あります。
CCNA認定の有効期間は「3年間」です。
IT技術は日進月歩で進化するため、資格保持者には知識のアップデートが求められます。
3年間の有効期間内に再認定を受けないと、資格は失効します。
CCNAの難易度は上がっている?下がっている?
一概には言えませんが、難易度の「質」が変わったと言えます。
2020年の改定前は、ルーティング&スイッチングの深い知識が問われましたが、現在はその部分が簡素化されました。
その代わり、試験範囲が「セキュリティ」「ワイヤレス」「自動化(プログラマビリティ)」にまで広がりました。
したがって、ネットワークの深い知識だけを比べれば難易度は下がったかもしれませんが、学ぶべき分野が広がったため、IT未経験者にとっては「学ぶべきことが多い」という意味で、難易度は上がった、あるいは「難しすぎる」と感じやすくなったと言えるでしょう。
まとめ
以上、CCNAは難しすぎると感じる方向けに、なぜそう感じるのか、どう対策すればいいのか、合格率はどの程度なのか、といった点を中心に解説してきました。
これまで解説してきた通り、CCNAは決して簡単な資格ではありません。
特に初心者の場合、確実な合格を目指すためにはスクールの利用も検討すべきかもしれません。

【スクール選びで後悔したくない方へ】
4年連続で人気No.1となっている「RUNTEQ」は、当ブログで調査した数多くのスクールの中でも大変おすすめです。なぜ選ばれ続けているのか、 その理由や受講生の評判については、以下の記事で詳しくまとめています。
※直接公式サイトを確認したい方はRUNTEQ公式サイトからどうぞ。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!



