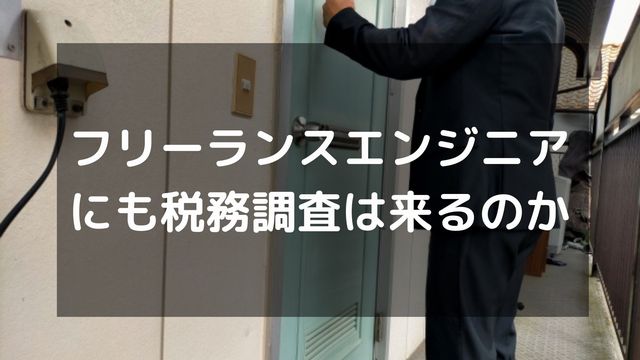「税務調査」と聞いても、「自分は大丈夫だろう」と考えているフリーランスエンジニアの方も多いのではないでしょうか。
しかし、フリーランスとして働くエンジニアにとっても、税務調査は決して他人事ではありません。
そこでこの記事では、フリーランスエンジニアにも税務調査が来るのか、来るとすればどれくらいの確率なのか、どんなフリーランスエンジニアが調査対象になりやすいのか、などについて詳しく解説していきます。
 |
|


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!
結論:フリーランスエンジニアも税務調査の対象になることがある

結論から言うと、フリーランスエンジニアも税務調査の対象になります。
会社員とは異なり、フリーランスは自身で確定申告を行うため、申告内容に誤りや不正がないかを確認するために税務調査が行われる可能性があるのです。
特に近年、働き方の多様化によりフリーランス人口が増加しており、国税庁も個人事業主への調査を強化する傾向にあります。
「エンジニアは狙われにくいだろう」
このような考えは危険でしょう。
国税庁は、KSK(国税総合管理)システムという全国の納税者情報を一元管理するシステムを活用しており、無申告や申告内容の異常値を効率的に把握することが可能です。
業種に関わらず、申告内容に不審な点があれば誰でも調査対象となる可能性があるため、日頃から正しい経理処理を心がけることが重要になります。
そもそも税務調査とは何か

税務調査とは、納税者が提出した確定申告書の内容が正しいかどうかを税務署が確認する手続きのことです。
これは、国の税収を確保し、公平な課税を実現するために行われます。
フリーランスエンジニアを含むすべての個人事業主や法人が対象です。
税務調査は、大きく分けて2つの種類があります。
| 任意調査 | 事前に税務署から電話などで連絡があり、日程を調整した上で行われる一般的な調査。納税者の同意のもとに行われるものの、正当な理由なく拒否することはできない。 |
| 強制調査 | 国税局査察部(マルサ)が、悪質な脱税の疑いがある場合に行う調査で、裁判所の令状を持って強制的に行われる。ただし、フリーランスエンジニアが対象となるケースは極めて稀。 |
ほとんどの税務調査は任意調査であり、申告内容について質問を受けたり、帳簿や請求書、領収書、通帳などの資料を提示したりすることが求められます。
目的はあくまで申告内容の確認なので、誠実に対応することが大切です。
税務調査の対象になりやすいフリーランスエンジニアの特徴

税務調査はランダムに選ばれることもありますが、特定の傾向を持つフリーランスエンジニアは調査対象として選定されやすくなります。
ここでは、特に注意すべき5つの特徴について解説します。
確定申告をしていない
確定申告をしていない、いわゆる「無申告」の状態は、税務調査の対象となる最も大きな要因の一つです。
収入があるにもかかわらず申告を怠ることは、明らかに法律違反となります。
税務署は、取引先の支払い調書や銀行口座の入出金履歴などから、個人の収入を把握することが可能です。
「バレないだろう」と安易に考えるのは非常に危険でしょう。
無申告が発覚した場合、本来納めるべきだった税金に加え、無申告加算税や延滞税といった重いペナルティが課せられます。
故意の所得隠しと判断されれば、さらに税率の高い重加算税の対象となる可能性すらあります。
フリーランスエンジニアとして活動する以上、所得の多少にかかわらず、毎年期限内に確定申告を行うことは絶対の義務だと認識してください。
売上がギリギリで1000万円を超えない年が続いている
売上が数年間にわたって1000万円をわずかに下回る水準で推移している場合も、税務署の注意を引く可能性があります。
なぜなら、売上が1000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者となり、消費税の納税義務が発生するからです。
この基準を回避するために、意図的に売上を少なく見せかけているのではないかと疑われることがあるのです。
例えば、年末に一部の売上を翌年に繰り越したり、取引先にお願いして請求書の発行を遅らせてもらったりする行為は、売上除外という不正行為にあたります。
国税庁は業種ごとの売上動向を把握しているため、不自然な売上の変動は発見されやすいでしょう。
経費が多すぎる
売上に対して経費の割合(経費率)が同業他者と比較して著しく高い場合、税務調査の対象になりやすくなります。
経費が多すぎると、その分所得が圧縮されて納税額が少なくなるため、税務署は「本当に事業に必要な経費なのか」という点に注目します。
特にフリーランスエンジニアの場合、自宅兼事務所で働いているケースが多く、家賃や水道光熱費、通信費などを経費として計上する際の家事按分が論点になりがちです。
事業で使用した割合を合理的な基準で説明できない場合、経費として認められない可能性があります。
また、家族との食事代や趣味の物品購入費など、明らかにプライベートな支出を経費に含めることはもちろん認められません。
領収書があれば何でも経費にできるわけではないことを理解し、事業関連性を明確に説明できるものだけを計上しましょう。
申告漏れが多い業種に該当する
国税庁は、毎年重点的に調査を行う業種を公表しています。
近年、IT関連の業種は申告漏れの金額が大きい傾向にあるとして、調査対象になりやすい業種の一つとされています。
特に、海外のクライアントとの取引がある場合や、インターネットを介した取引が多い場合、お金の流れが複雑になりがちで、申告漏れが発生しやすいと見なされることがあります。
フリーランスエンジニアは、新しい技術や働き方が次々と生まれる分野であり、税務上の取り扱いが明確でないケースも少なくありません。
例えば、仮想通貨での報酬受け取りや、海外プラットフォーム経由での収入などは、正しく申告できているか特に注意が必要です。
自分が該当する業種が重点調査対象になっていないか、国税庁の発表などを確認しておくとよいでしょう。
顧問税理士がいない
確定申告を税理士に依頼せず、すべて自分で行っている場合も、税務調査の対象となる可能性が相対的に高まることがあります。
税理士が作成・署名した申告書は、専門家によるチェックを経ているため、税務署からの信頼性が高くなります。
特に「書面添付制度」を利用している場合、申告書の作成にあたって税理士がどのような計算・整理・相談を行ったかを具体的に記載した書面を添付するため、申告内容の信頼性がさらに向上します。
これにより、税務調査自体が省略されたり、調査があっても簡易な聞き取りで済んだりするケースが多くなります。
顧問税理士がいないことが直接的な調査理由になるわけではありませんが、申告内容の正確性を担保するという意味で、税理士の関与は有効な対策の一つと言えるでしょう。
フリーランスエンジニアに税務調査が入る確率は?

フリーランスエンジニア個人に限定した税務調査の確率に関する公式なデータはありませんが、国税庁が公表している個人事業主全体のデータからおおよその傾向を推測できます。
国税庁の「令和4事務年度 所得税及び消費税調査等の状況」によると、所得税の実地調査(実際に自宅や事務所に赴いて行われる調査)の件数は、申告納税者のうち約0.5%に対して行われています。
数字だけ見ると「1000人に5人程度」となり、低いように感じるかもしれません。
しかし、これはあくまで全体の平均値です。
先述した「税務調査の対象になりやすい特徴」に複数当てはまる場合は、調査対象に選ばれる確率が平均よりも高まると考えられます。
特に、無申告者や海外取引がある事業者、急激に売上が伸びた事業者などに対しては、より積極的に調査が行われる傾向があります。
確率が低いからといって安心するのではなく、誰もが調査対象になりうると考え、日頃から誠実な申告を心がけることが重要です。
フリーランスエンジニアに税務調査が入るとどうなるのか

もし税務調査の連絡が来たら、どのようなことが起こるのでしょうか。
ここでは、調査の基本的な流れと、申告内容に不備があった場合の影響について解説します。
確定申告の内容が正しいかどうかチェックされる
税務調査の主な目的は、過去の確定申告(通常は直近3年分、場合によっては5〜7年分)の内容が、帳簿や証拠資料と一致しているかを確認することです。
調査官は、まず事業の概要や経理の状況についてヒアリングを行います。
その後、以下のような書類を基に、売上の計上漏れや架空経費の計上がないかなどを詳細にチェックします。
- 総勘定元帳、仕訳帳などの会計帳簿
- 請求書、領収書、レシートの控え
- 預金通帳(事業用・プライベート用ともに)
- 契約書
- 納品書
特に、経費についてはその支出が本当に事業に必要なものだったのか、プライベートな支出が含まれていないかといった点を厳しく見られます。
質問に対しては、曖昧な回答を避け、事実に基づいて正直に説明することが求められます。
税務調査に協力するため丸一日拘束される
税務調査は、通常1〜2日間にわたって行われます。
調査当日は、朝10時頃に調査官が自宅や事務所を訪れ、夕方まで帳簿や資料の確認、ヒアリングなどが行われます。
この間、フリーランスエンジニア本人は調査に立ち会う必要があるため、実質的に丸一日仕事ができなくなります。
調査官からの質問に答えたり、要求された資料を探したりと、精神的な負担も大きいものです。
顧問税理士がいる場合は、調査の立ち会いを依頼することで、専門的な観点から調査官とのやり取りを任せることができ、本人の負担を大幅に軽減できます。
調査中は他の業務が完全にストップしてしまうため、事業への影響も考慮しておく必要があるでしょう。
申告内容に不備があれば追徴課税される
調査の結果、申告内容に誤りや漏れが指摘され、修正申告が必要になった場合、本来納めるべきだった税額に加えて、ペナルティとして「附帯税」が課せられます。
これを追徴課税と呼びます。
附帯税には以下のような種類があり、状況に応じて複数の税金が課されることもあります。
| 附帯税の種類 | 内容 | 主な税率 |
| 過少申告加算税 | 期限内に申告したが、納税額が少なかった場合に課される。 | 新たに納める税額の10%(一定額を超えると15%) |
| 無申告加算税 | 期限までに申告しなかった場合に課される。 | 納付すべき税額の15%(一定額を超えると20%) |
| 重加算税 | 意図的に事実を隠蔽・仮装した場合に課される、最も重いペナルティ。 | 過少申告加算税に代えて35%、無申告加算税に代えて40% |
| 延滞税 | 法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて課される利息。 | 年率で変動(2025年時点では最大年8.7%程度) |
出典:財務省「加算税制度の概要①(基本情報)」
このように、申告に不備があると金銭的な負担が大幅に増えてしまいます。
税務調査を受けてしまったフリーランスエンジニアの体験談
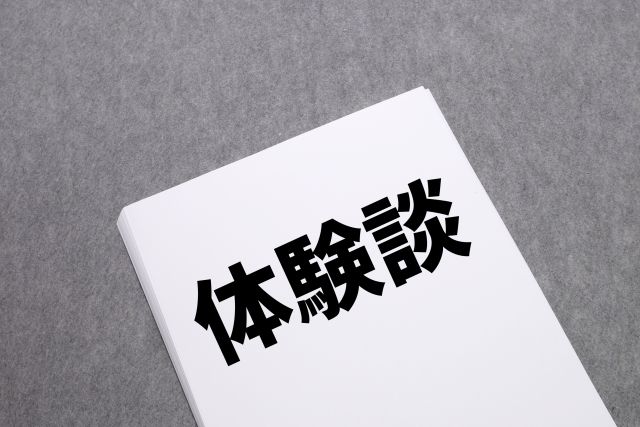
ここでは、実際に税務調査を経験したフリーランスの方の体験談を3つ紹介します。
具体的な事例を知ることで、税務調査をより身近な問題として捉えることができるでしょう。
事前準備と雑談で流れを掴んだIT企業経営者の例
あるIT企業の経営者は、税務調査の連絡を受けてから1ヶ月半の準備期間で、顧問税理士と入念な打ち合わせを行いました。
調査当日は、あえて調査官が作業しにくいような低いテーブルとソファの席へ案内。
さらに、調査開始後の雑談を1時間半も続けることで、調査の実時間を短縮し、和やかな雰囲気を作ることに成功したそうです。
結果として、指摘事項はあったものの、事前のシミュレーションと当日のコミュニケーション戦略が功を奏し、比較的穏便に調査を終えることができました。
これは、準備と当日の立ち回りの重要性を示す好例と言えるでしょう。
経費の家事按分を厳しく指摘されたデザイナーの例
自宅兼事務所で働く、とあるWebデザイナーの方が、売上が1000万円を超えた年に税務調査の対象となりました。
調査では、特に家賃や水道光熱費などの家事按分の根拠について、厳しく追及されたとのことです。
仕事部屋の使用面積や使用時間などを基に算出した割合を提示しましたが、調査官からは「その計算は客観的とは言えない」と一部を否認されてしまいました。
また、友人との食事代を会議費として計上していた点も指摘され、プライベートな支出と見なされました。
最終的には修正申告に応じ、数十万円の追徴課税を支払うことになったそうです。
無申告で多額の追徴課税を支払ったエンジニアの例
数年間、確定申告をしていなかったフリーランスエンジニアのもとに、ある日突然、税務署から連絡がありました。
税務署は取引先への調査(反面調査)や銀行口座の履歴から、無申告である事実を完全に把握していました。
調査では過去5年分にさかのぼって所得を計算され、本来の所得税と住民税に加え、重加算税と延滞税を含む多額の追徴課税を命じられました。
手元に資金がなく、分割での納税を余儀なくされたとのことです。
この事例は、無申告のリスクがいかに大きいかを物語っています。
税務調査が来ないようにフリーランスエンジニアができる対策
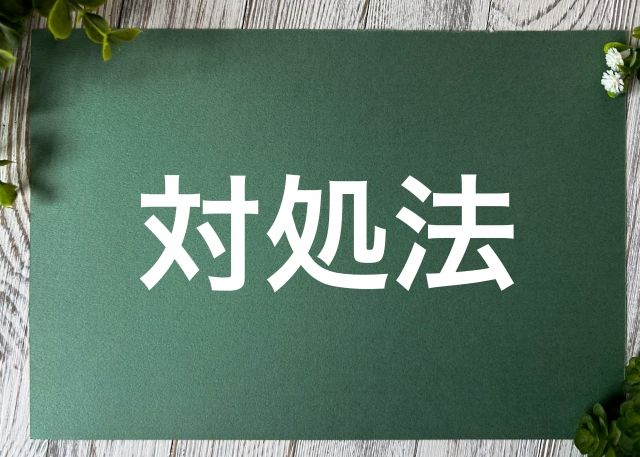
税務調査はいつ連絡が来るか分かりませんが、日頃から適切な対策を講じることで、調査対象に選ばれるリスクを低減させることが可能です。
ここでは、フリーランスエンジニアが実践すべき4つの対策を紹介します。
毎年必ず確定申告を行う
最も基本的かつ重要な対策は、毎年必ず期限内に確定申告を行うことです。
所得があるにもかかわらず申告をしない「無申告」は、税務調査の最大のターゲットとなります。
たとえ所得が少なく、納税額が発生しない場合でも、申告の義務がある場合は必ず手続きをしてください。
確定申告には、簡易な白色申告と、複式簿記での記帳が必要な代わりに最大65万円の特別控除などが受けられる青色申告があります。
節税メリットの大きい青色申告を選択し、会計ソフトなどを活用して日頃から正確な帳簿を作成する習慣をつけることが、結果的に税務調査への備えにも繋がるでしょう。
売り上げ調整をしない
消費税の納税義務が発生する「売上1000万円」のラインを意識するあまり、意図的に売上を翌年に繰り越すなどの調整行為は絶対に行わないでください。
これは売上除外という脱税行為にあたり、税務調査で発覚した場合には重いペナルティが課されます。
売上は、取引が確定した時点(納品やサービスの提供が完了した時点)で計上するのが原則です。
請求書の発行日や入金日基準ではない点に注意しましょう。
税務署は過去の申告データや同業他社の状況と比較して、不自然な売上の動きを把握しています。
目先の納税を免れるための安易な調整は、将来的に大きなリスクを招くことを理解してください。
経費率を適切な割合にして申告する
経費の計上は節税の基本ですが、過度な計上は税務署の疑念を招きます。フリーランスエンジニアの経費率は業態にもよりますが、一般的には40%〜50%程度が目安とされています。
これを大幅に超えるような経費率の場合は、その内訳を合理的に説明できる準備が必要です。
特に、自宅兼事務所の家賃や光熱費などを経費にする際は、事業での使用割合(面積や時間など)を明確な根拠に基づいて計算する「家事按分」を適切に行いましょう。
また、私的な飲食代や旅行費、趣味の物品などを事業経費として計上することはできません。
「これは経費になるだろうか」と迷った際は、事業に直接関連しているかどうかを客観的に判断する癖をつけてください。
顧問税理士と契約する
税務に関する最も確実な対策は、税金の専門家である税理士と顧問契約を結ぶことです。
顧問税理士がいれば、日々の記帳指導から正確な確定申告書の作成、さらには効果的な節税対策まで、幅広くサポートしてもらえます。
そして、税理士が申告書を作成し、申告内容の正当性を保証する「書面添付」を付与すれば、税務署からの信頼度が格段に上がり、税務調査のリスクを大幅に下げることが可能です。
万が一、税務調査の対象となった場合でも、専門家として調査に立ち会い、的確な対応をしてくれるため、精神的・時間的な負担を大きく軽減できます。
費用はかかりますが、安心感と本業に集中できる環境を得られるという点で、非常に価値のある投資と言えるでしょう。
フリーランスエンジニアが万が一税務調査に入られたらどうすべき?
対策を講じていても、税務調査の対象となってしまう可能性はゼロではありません。
もし税務署から電話などで調査の連絡が来たら、慌てず冷静に対応することが大切です。
まず、電話で調査官の所属部署と氏名、調査の目的、対象となる税目、対象期間、希望日時などを正確に聞き取り、メモを取りましょう。
その場で即答する必要はありません。
「顧問税理士と相談してから折り返します」と伝え、一度電話を切るのが賢明です。
次に、すぐに顧問税理士に連絡し、状況を説明して今後の対応を相談します。
顧問税理士がいない場合は、このタイミングで税務調査に強い税理士を探して相談することをおすすめします。
専門家のサポートがあるかないかで、調査の結果が大きく変わることもあります。
そして、調査当日までに、指摘された対象期間の帳簿や請求書、領収書、通帳などの関係書類を整理して準備しておきます。
調査当日は、税理士に立ち会ってもらい、質問には正直かつ簡潔に答えることを心がけてください。
不要なことまで話したり、曖昧な返答をしたりするのは避けましょう。
誠実な態度で協力することが、調査を円滑に進める上で最も重要です。
まとめ
フリーランスエンジニアにとって、税務調査は決して他人事ではありません。
売上が順調に伸びている方や、経費の計上に不安がある方は、特に注意が必要です。
税務調査の対象となる確率は低いかもしれませんが、一度対象となれば時間的にも精神的にも大きな負担がかかり、場合によっては多額の追徴課税が発生するリスクがあります。
誠実な申告と適切な経理処理は、フリーランスエンジニアが安心して事業を継続していくための土台となりますので、是非心掛けるようにしてください。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!