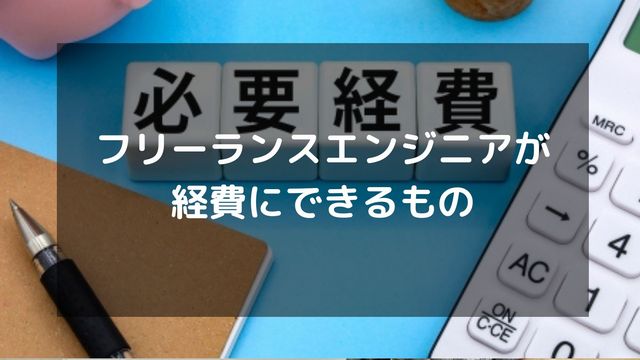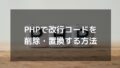フリーランスエンジニアとして独立すると、会社員時代にはなかった「経費」という概念と向き合うことになります。
経費を正しく計上することは、納める税金を減らし、手元に残る資金を最大化するために不可欠な知識です。
しかし、「何が経費になるのか」「いくらまで経費にしてよいのか」といった疑問を持つ方も少なくないでしょう。
そこでこの記事では、フリーランスエンジニアが経費にできる具体的な項目や、経費にできないものの例、適切な経費率などについて詳しく紹介しますので、ぜひ確定申告の準備に役立ててください。
 |
|


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!
フリーランスエンジニアとして活動するのに必要な費用はすべて経費にできる

フリーランスエンジニアが経費を考える上での大原則は、「仕事に関連する支出であるか」という点です。
つまり、売上を得るために直接的、あるいは間接的に必要となった費用は、基本的にすべて経費として計上することが可能です。
例えば、プログラミング作業に使うパソコンや、クライアントとの打ち合わせに向かうための交通費などがこれにあたります。
重要なのは、その支出が「なぜ事業に必要なのか」を客観的かつ合理的に説明できることです。
税務調査などで質問された際に、個人的な趣味の支出ではなく、あくまで事業活動の一環であることを明確に答えられなければなりません。
この「事業関連性」という基準を常に意識することが、適切な経費計上の第一歩です。
プライベートな支出と事業用の支出は、明確に区別して管理する習慣をつけてください。
フリーランスエンジニアの経費はいくらまで計上可能?
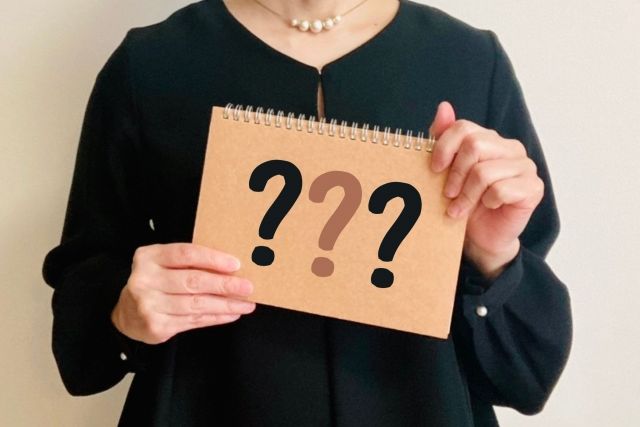
フリーランスエンジニアが計上できる経費の金額に、法律で定められた明確な上限はありません。
理論上は、事業に必要な費用であればいくらでも経費として計上できます。
しかし、これは「無制限に何でも経費にできる」という意味ではないので注意が必要です。
税務署がチェックする際に重視するのは、売上と経費のバランス、つまり「経費率」です。
例えば、年間の売上が500万円であるにもかかわらず、経費が450万円もかかっている場合、「本当にすべてが事業に必要な支出なのか」と疑問を持たれる可能性があります。
特に、接待交際費や旅費交通費などが不自然に多いと、税務調査の対象になりやすくなるかもしれません。
経費の上限額を気にするよりも、「この支出は事業収益を上げるために本当に必要だったか」という視点で判断することが大切です。
フリーランスエンジニアが経費にできるものの例

フリーランスエンジニアの業務に関連する支出は多岐にわたります。
ここでは、経費として認められる具体的な項目を例示し、それぞれの計上におけるポイントを解説していきます。
パソコン・周辺機器の購入費
フリーランスエンジニアにとって必須の仕事道具であるパソコンや、モニター、キーボード、マウスといった周辺機器の購入費用は経費にできます。
ただし、その取得価額によって会計処理が異なる点に注意してください。
| 10万円未満の場合 | 勘定科目を「消耗品費」として、購入した年に全額を経費計上します。 |
| 10万円以上の場合 | 原則として「減価償却資産」として扱います。法定耐用年数(個人のパソコンは4年)にわたって、毎年少しずつ費用を計上していく「減価償却」という手続きが必要です。 |
ただし、青色申告を行っているフリーランスには特例があります。
「少額減価償却資産の特例」を活用すれば、30万円未満の資産であれば購入した年に一括で経費計上することが可能です。(年間合計300万円まで)
この特例の適用期限は、2026年3月31日までとなっています。
この制度の詳細は、 国税庁の「減価償却のあらまし」にて詳しく解説されています。
インターネットや電話といった通信費
業務で使用するインターネット回線の料金や、スマートフォンの通信費、サーバー代、ドメイン費用なども経費の対象です。
これらは事業運営に不可欠なインフラ費用であり、全額を経費として計上できるケースが多いでしょう。
もし、自宅のインターネット回線や個人のスマートフォンを仕事とプライベートで兼用している場合は、「家事按分」という考え方が必要になります。
例えば、1日のうち8時間を仕事、16時間をプライベートで利用しているなら、通信費の3分の1(8時間÷24時間)を経費として計上するなど、合理的な基準で事業使用分を算出してください。
この割合は、自身の業務実態に合わせて設定することが重要です。
自宅の家賃
自宅を事務所として利用している場合、家賃の一部を経費として計上できます。
この場合も「家事按分」の考え方を用います。
家賃の按分割合を算出するには、主に2つの基準が使われます。
| 床面積で按分する | 自宅全体の床面積のうち、仕事専用で使っているスペースの割合で計算する方法です。 |
【例:自宅全体が50㎡で、仕事部屋が10㎡の場合】 10㎡ ÷ 50㎡ = 20% 家賃が15万円なら、15万円 × 20% = 3万円が経費となります。 |
| 使用時間で按分する | 1日のうち、業務を行っている時間の割合で計算します。 | 【例:1日8時間業務を行う場合】 8時間 ÷ 24時間 ≒ 33%なので、家賃が15万円なら、15万円 × 33% = 4万9500円が経費となります。 |
どちらの基準を用いるかは自分で選択できますが、税務署に質問された際に、その割合の根拠を明確に説明できるようにしておくことが大切です。
旅費交通費
クライアントとの打ち合わせ場所への移動や、セミナー参加のための移動など、業務に関連する移動で発生した費用は「旅費交通費」として経費に計上可能です。
対象となるのは、電車代、バス代、タクシー代、新幹線代、飛行機代、有料道路の料金、駐車場の料金などです。
電車代のように領収書が出ない場合は、出金伝票に「日付」「行き先」「目的」「金額」などを記録しておくことで、経費計上の証拠とすることができます。
交通系ICカードの利用履歴を印刷して保管しておくのも有効な手段でしょう。
通勤という概念がないフリーランスにとって、業務のための移動はすべてが経費の対象となりえます。
水道光熱費
自宅兼事務所で仕事をしている場合、電気代や水道代、ガス代といった水道光熱費も家賃と同様に家事按分して経費に計上できます。
按分の基準としては、業務時間を用いるのが一般的です。
例えば、1ヶ月の電気代が15,000円で、1日の労働時間が8時間、月の労働日数が20日だったとしましょう。
事業使用時間の割合を「(8時間 × 20日) ÷ (24時間 × 30日) ≒ 22%」のように算出し、15,000円にこの割合を掛けた3,300円を経費とします。
エンジニアの業務は特に電気の使用量が多いため、他の業種に比べて少し高めの按分割合を設定することも、実態に即していれば合理的な判断といえるかもしれません。
書籍の購入費
プログラミング言語の技術書や、デザイン関連の専門書、業界動向を把握するためのビジネス書なども、フリーランスエンジニアとしてスキルアップしたり情報を集めたりするのに必要です。
こういった書籍の購入費用は「新聞図書費」として経費にできます。
ただし、趣味の小説や、業務とは全く関係のない雑誌などは経費として認められません。
あくまで「エンジニアとしての業務遂行能力を高めるために必要であったか」が判断基準となります。
どのプロジェクトのために、どのような知識を得る目的で購入したのかを説明できれば、問題なく経費として計上できるでしょう。
電子書籍の購入ももちろん対象になりますので、購入履歴がわかるものを保存しておくようにしてください。
セミナー参加費
最新技術の動向を学ぶための勉強会や、スキルアップを目的とした有料セミナー、異業種交流会への参加費なども経費として認められます。
これらは「研修費」や「諸会費」といった勘定科目で処理することが多いです。
セミナー参加は、新たな知識を得るだけでなく、将来の顧客となりうる人脈を築く機会でもあります。
そのため、事業の発展に貢献する活動として、その費用は経費と見なされるのです。
参加したセミナーの名称、内容、目的などを記録として残しておくと、より説得力が増すでしょう。オンラインセミナーの参加費も同様に経費計上が可能です。
接待交際費
取引先との関係を円滑にするための打ち合わせでの飲食代や、感謝の気持ちを伝えるためのお中元・お歳暮などの贈答品の費用は「接待交際費」として経費に計上できます。
個人事業主の場合、法人と違って接待交際費に上限はありません。
しかし、常識の範囲を超える高額な支出や、事業との関連性が薄い私的な会食は経費として認められない可能性が高いでしょう。
経費として計上するためには、領収書に「いつ」「誰と」「何の目的で」支出したのかをメモしておくことが非常に重要です。
友人との食事代を経費にすることはできませんので、公私の区別を徹底してください。
10万円未満の消耗品の購入費
業務で使用する比較的に少額な物品の購入費用は「消耗品費」として経費計上します。
10万円未満のものがこれに該当し、購入した年に全額を経費にすることが可能です。
フリーランスエンジニアの場合、以下のようなものが考えられます。
- マウス、キーボード、Webカメラ
- USBメモリ、外付けHDD
- プリンターのインク、コピー用紙
- 文房具全般
- 有料のソフトウェアやアプリケーション
- 作業用のデスクや椅子(10万円未満のもの)
これらの細かな支出も、年間で合計すると大きな金額になります。
一つひとつ領収書を保管し、忘れずに計上するようにしましょう。
外注費
自身のスキルだけでは対応できない業務や、手が回らない作業を他のフリーランスや業者に依頼した場合、その対価として支払った費用は「外注費」として経費に計上できます。
例えば、Webサイト制作案件で、デザイン部分をWebデザイナーに、コーディング部分を別のエンジニアに、といった形で業務を委託するケースが考えられるでしょう。
外注費を計上する際は、誰に、どのような業務を、いくらで依頼したのかを明確にする必要があります。
そのため、契約書や発注書、納品物、請求書といった一連の書類をきちんと保管しておくことが重要です。
これらの書類は、単なる取引の証拠だけでなく、適正な経費計上の根拠ともなります。
租税公課(自動車税や印紙税など)
「租税公課」とは、国や地方自治体に納める税金(租税)と、公共団体などへ支払う会費や手数料(公課)を合わせた勘定科目です。
フリーランスエンジニアが支払う税金の中にも、経費にできるものとできないものがあります。
【経費にできる租税公課の例】
- 個人事業税
- 固定資産税(事業用部分)
- 自動車税(事業用部分)
- 印紙税(契約書などに貼付するもの)
- 消費税(税込経理方式の場合)
- 不動産取得税(事業用不動産)
これらの税金は、事業を運営する上で発生するコストとして考えられるため、経費として認められます。
一方で、所得税や住民税は経費になりませんので注意が必要です。
出張時の宿泊費
クライアントが遠方にいる場合や、地方で開催されるセミナーに参加する場合など、業務上の理由で宿泊が必要になった際のホテル代や旅館代は「旅費交通費」として経費にできます。
出張に伴う交通費も同様です。
ただし、経費として認められるのは、あくまで業務に必要な常識的な範囲の宿泊に限られます。
不必要に豪華なスイートルームに宿泊した場合などは、その全額が認められず、一部が否認される可能性もあるでしょう。
また、出張の目的や日程、訪問先などを明確に記録し、その必要性を説明できるようにしておくことが大切です。
家族旅行のついでに少しだけ仕事をした、というようなケースは経費として認められませんので、注意してください。
広告宣伝費
自身のスキルやサービスを広く知ってもらい、新たな顧客を獲得するためにかかった費用は「広告宣伝費」として経費計上できます。
フリーランスエンジニアにとって、自己PRは事業を継続させる上で非常に重要な活動です。
具体的には、以下のような費用が該当します。
- ポートフォリオサイトやブログのサーバー代・ドメイン代
- Web広告の出稿費用
- 名刺の作成費用
- パンフレットやチラシの作成費用
- ロゴデザインの依頼費用
これらの活動は、将来の売上につながる投資と見なされます。
支出した費用の目的が、事業の宣伝や顧客獲得であることを明確に説明できれば、問題なく経費として認められるでしょう。
フリーランスエンジニアが経費にできないものの例

事業に関連する費用が経費になる一方で、当然ながら経費として認められない支出も存在します。
ここでは、フリーランスエンジニアが誤って経費に計上してしまいがちな、代表的な項目を見ていきましょう。
所得税や住民税
フリーランスが納める税金の中でも、所得税と住民税は経費に計上することができません。
これらの税金は、事業活動によって得られた「所得(利益)」に対して課されるものです。
つまり、経費を差し引いた後の利益から支払うべきものであり、事業を行うためのコストとは見なされないのです。
同じ税金でも、個人事業税や固定資産税(事業使用分)などが経費になるのとは性質が異なります。
所得税や住民税を経費としてしまうと、税金の計算が永久に終わらなくなってしまいます。
確定申告の際には、これらを誤って経費に含めないよう、くれぐれも注意しましょう。
引っ越し費用
自宅兼事務所で働いているフリーランスが引っ越しをした場合、その費用は原則として経費にできません。
引っ越しは、個人の生活拠点を移すための行為と見なされるため、プライベートな支出と判断されるのが一般的です。
ただし、例外もあります。
例えば、事業規模の拡大に伴い、より広い仕事スペースを確保するために事務所専用の物件へ移転する、といったケースです。
このように、引っ越しの目的が明らかに事業のためであると客観的に証明できる場合は、経費として認められる可能性もあるでしょう。
しかし、その判断は非常に厳格なため、自宅兼事務所の引っ越し費用は基本的に経費にならないと考えておくのが無難です。
家具や家電
仕事部屋に置くデスクや椅子は経費にできますが、同じ家具でもリビングに置くソファやダイニングテーブルなどは、原則として経費にできません。
家電も同様で、仕事で使うパソコンは経費になりますが、プライベートで見るテレビや、料理に使う電子レンジなどは対象外です。
ここでも判断基準は「事業専用で使っているか」という点になります。
生活と仕事の両方で使う可能性があるものは、経費として認められにくい傾向にあります。
もし経費計上する場合は、家事按分するなど合理的な説明が必要ですが、税務署から否認されるリスクも考慮しておくべきでしょう。
その他のプライベートな出費
上記以外にも、経費にならないプライベートな支出は数多く存在します。
例えば、スーツや仕事用の衣服代です。
これらは仕事以外でも着用できる可能性があるため、原則として経費にはなりません。(ただし、作業着など明らかに業務用とわかるものは除く)
また、事業主一人のみの福利厚生費(人間ドックの費用など)や、日々のランチ代といった食費も、事業に直接必要な費用とは認められません。
国民健康保険料や国民年金保険料も経費にはなりませんが、これらは「社会保険料控除」という形で所得から控除することができます。
事業の経費と個人の支出、そして所得控除の対象となるものを正しく区別することが重要です。
フリーランスエンジニアが意識すべき経費率

経費率とは、売上(収入)に対して経費がどれくらいの割合を占めているかを示す指標です。
計算式は「経費 ÷ 売上 × 100」で算出されます。
この経費率を意識することは、自身の事業の収益性を把握し、税務上のリスクを管理する上で役立ちます。
フリーランスエンジニアの経費率は、一般的に40%から50%程度が目安と言われることがありますが、これはあくまで一般的な数値に過ぎません。
例えば、在宅で常駐案件をこなしているエンジニアと、積極的に機材投資を行いながら自社サービス開発を目指すエンジニアとでは、経費の構造が全く異なります。
重要なのは、自身の事業モデルにおいて経費率が妥当な水準にあるか、そして前年と比較して不自然な増減がないかを確認することです。
経費率が極端に高い場合は、税務署から「プライベートな支出が混入しているのではないか」と疑われる一因になりかねないので注意してください。
フリーランスエンジニアが経費を計上する際の注意点

経費を正しく計上し、節税効果を最大限に得るためには、いくつかの重要な注意点を押さえておく必要があります。
ここでは、確定申告で慌てないために、日頃から意識しておくべきポイントを3つ解説します。
必ず領収書やレシートを保存しておく
経費を計上する上で、最も基本的なルールが「証拠となる書類を保存すること」です。
原則として、すべての経費は領収書やレシートによってその支払いを証明できなければなりません。
これらの書類は、白色申告の場合は5年間、青色申告の場合は7年間の保存が義務付けられています。
もし領収書をもらい忘れたり、紛失したりした場合は、出金伝票に「日付」「支払先」「内容」「金額」を記録しておくことで代用できます。
クレジットカードの利用明細や銀行の振込履歴も有力な証拠となるでしょう。
日頃から書類を整理し、いつでも提示できる状態にしておくことが、税務調査への備えにもなります。
按分割合を適切にする
自宅の家賃や水道光熱費、通信費などを経費にする「家事按分」は、フリーランスにとって重要な節税テクニックです。
しかし、その按分割合は、客観的かつ合理的な基準に基づいて設定しなければなりません。
なぜその割合にしたのか、その根拠を税務署にきちんと説明できるように準備しておきましょう。
「なんとなく3割」といった曖昧な基準ではなく、「仕事部屋の面積が全体の25%だから」「平日は平均8時間仕事をしているから」といった具体的な根拠を持つことが重要です。
一度決めた按分割合は、事業の実態に変化がない限り、継続して適用するのが望ましいでしょう。
経費率を高くしすぎない
経費に上限はないものの、売上に対して経費率が極端に高い状態は避けるべきです。
同業種の平均的な経費率から大きくかけ離れていると、税務署のシステムが異常値として検知し、税務調査の対象に選ばれる可能性が高まります。
もちろん、大規模な設備投資を行った年など、正当な理由があって経費率が高くなることは問題ありません。
しかし、毎年継続して利益がほとんど出ていないような申告を続けていると、事業としての実態を疑われることにもなりかねません。
経費を漏れなく計上することは大切ですが、同時に売上を伸ばし、事業として利益を出す意識を持つことも忘れないでください。
まとめ
以上、フリーランスエンジニアが経費にできるもの、できないもの、そして経費を計上する際の注意点について詳しく解説しました。
適切な経費計上は、手元に残るお金を増やすだけでなく、自身の事業の財務状況を正確に把握することにも繋がります。
領収書を確実に保存し、家事按分の根拠を明確にするなど、日頃からの丁寧な管理を心がけ、年に一度の確定申告をスムーズに乗り切りましょう。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!