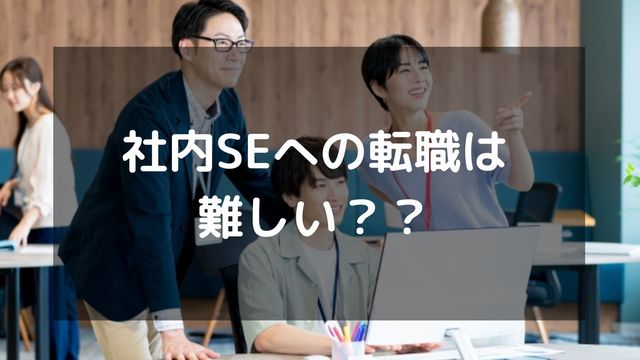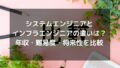社内SEへの転職は、転職市場においては「難しい」と言われることが少なくありません。
社内SEの求人案件は、人気が高い一方で求人数が限られているため、多くのITエンジニアにとって狭き門となっています。
そこでこの記事では、社内SEへの転職がなぜ難しいのかについて、詳しく掘り下げていきます。
同時に、社内SEが「勝ち組」と称される魅力や、厳しい選考を突破して社内SEへの転職を成功させるための具体的な戦略についても解説しますので、是非参考にしてください。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!
社内SEへ転職するのが難しい理由

社内SEへの転職が困難とされる背景には、職種特有の事情がいくつか存在します。
人気、求人数、求められるスキルセット、そして未経験者の採用ハードルといった複数の要因が絡み合っているのが実情です。
以下の項目で、詳しく解説していきます。
「楽すぎ」「勝ち組」とも言われるほど働きやすく人気がある
社内SEは「勝ち組」や「楽すぎ」といった言葉で表現されることがあるほど、ITエンジニアにとって魅力的な職種の一つです。
クライアントが自社の社員であるため、無理な納期設定が少なく、スケジュールを調整しやすい傾向にあるという点が、勝ち組・楽すぎと言われる最大の理由です。
結果として、ワークライフバランスを保ちやすく、プライベートの時間を確保しやすくなります。
また、自社の経営課題の解決に直接貢献できるため、仕事の成果がわかりやすく、大きなやりがいを感じられるという点にも魅力を感じる人が多いです。
このような働きやすさや魅力から、多くのエンジニアが社内SEへの転職を希望します。
SIerやSESなどのエンジニアが、キャリアアップや働き方改善を目指して応募するケースも少なくありません。
その結果、一つの求人に対して応募が殺到し、競争が激化することで転職難易度を押し上げているのです。
社内SEの求人自体があまり多くない
社内SEの転職が難しい大きな要因として、求人の絶対数が少ない点が挙げられます。
一般的に、事業会社における情報システム部門は、会社の規模に対して少人数で構成されることがほとんどです。
そのため、欠員が出た場合や、大規模なシステム導入プロジェクトが立ち上がった場合などにしか募集がかからない傾向があります。
システム開発を専門とするIT企業が常にエンジニアを募集している状況とは対照的と言えるでしょう。
特に、待遇や労働環境が良いとされる大手企業や優良企業の社内SE求人は、非公開求人として転職エージェント経由で募集されることも多く、市場に出回る前に採用枠が埋まってしまうケースも珍しくありません。
このように、限られたポストを多くの希望者で争う構図が、転職の難しさに拍車をかけています。
求められるスキルが幅広い
社内SEの業務は、特定の技術領域に限定されません。
非常に広範な知識とスキルが求められるジェネラリスト的な役割を担います。
社内SEに求められる主なスキルは以下の通りです。
- 経営課題をヒアリングし、ITを活用した解決策を企画する能力
- サーバー、ネットワークの設計、構築、運用保守といったインフラの知識
- 業務システムの開発、導入、改修、運用保守のスキル
- 情報セキュリティポリシーの策定やインシデント対応
- 外部ITベンダーの選定、交渉、プロジェクト進捗管理
- 社員からのPCやシステムに関する問い合わせといったヘルプデスク作業
- 経営層から現場社員まで、様々な立場の人と円滑に意思疎通を図る能力
このように、技術的なスキルだけでなく、ビジネスへの理解や高度なコミュニケーション能力まで必要とされるのです。
また、企業側が求めるスキルセットと、応募者の経験が完全にマッチしにくい点も、転職を難しくする一因となっています。
未経験から転職するのが困難
社内SEは、少数精鋭の組織であることが多く、手厚い研修制度を設けている企業は限られます。
そのため、採用においては入社後すぐに活躍できる即戦力が求められるのが一般的です。
これまでに解説した通り、求人数が少なく競争率が高いこと、そして求められるスキルが広範であることから、IT業界での実務経験がない未経験者が社内SEとして採用されるのは極めて困難と言わざるを得ません。
全くの未経験から社内SEを目指す場合、まずはSIerやSES企業などで開発やインフラ運用の実務経験を数年間積むことが、キャリアパスの第一歩となるでしょう。
現場で技術力とプロジェクト経験を身につけた後、キャリアアップとして社内SEへの転職を目指すのが現実的なルートです。
そもそも社内SEとは

社内SEへの転職を考える上で、まずはその役割と仕事内容を正しく理解することが重要です。
ここでは、社内SEに関する基本的な部分について解説していきます。
社内SEの仕事内容
社内SEは、自社内の情報システムに関するあらゆる業務を担当するエンジニアです。
その役割は、会社のIT戦略の策定から、日々のヘルプデスク業務まで多岐にわたります。
主な仕事内容は以下の通りです。
| 企画・戦略 | 経営層や各事業部門と連携し、事業課題を解決するためのIT戦略を立案、システム導入の企画・提案を行う。 |
| 開発・導入 | 新規システムの要件定義、設計、開発、導入プロジェクトの管理。外部ベンダーに開発を委託する場合は、ベンダーコントロールを担う。 |
| 運用・保守 | 既存の社内システム(基幹システム、情報系システムなど)やインフラ(サーバー、ネットワーク)が安定稼働するように監視・メンテナンスを行う。 |
| ヘルプデスク・サポート | 社員からのPC操作、ソフトウェア、システムに関する問い合わせに対応。トラブルシューティングやITリテラシー向上のための教育も実施する。 |
| セキュリティ管理 | 情報セキュリティポリシーの策定・運用、ウイルス対策、不正アクセス監視、セキュリティインシデントへの対応などを行う。 |
| IT資産管理 | PC、サーバー、ソフトウェアライセンスなどのIT資産を管理し、購入や廃棄の計画を立てる。 |
このように、会社のIT環境全体を支える重要な役割を担っており、その業務範囲は非常に広いことが特徴です。
社内SEに向いている人の特徴
社内SEとして活躍するには、技術力だけでなく、ヒューマンスキルも同様に重要視されます。
以下のような特徴を持つ人は、社内SEに向いていると言えるでしょう。
経営層、現場の社員、外部ベンダーなど、様々な立場の人と関わるため、相手の意図を正確に汲み取り、専門的な内容を分かりやすく説明する能力が不可欠です。
各部署からの異なる要望をまとめたり、ベンダーと価格や納期を交渉したりする場面が多くあります。利害関係を調整し、プロジェクトを円滑に進める力が求められます。
単にシステムを作るだけでなく、「ITでいかに事業に貢献するか」という視点が重要です。自社のビジネスモデルや業界動向に関心を持ち、経営課題の解決に主体的に取り組む姿勢が評価されます。
インフラからアプリケーション、セキュリティまで、幅広い技術領域をカバーする必要があります。特定の技術に固執せず、新しい技術やトレンドを積極的に学ぶ姿勢が大切になります。
直接的な売上を上げる部署ではありませんが、社内の業務効率化や生産性向上を通じて、会社全体を支える役割にやりがいを感じられる人に向いています。
その他にも、向いている人の特徴はいろいろあります。
以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方は是非参考にしてください。
なぜ社内SEは人気があるのか

社内SEは、多くのITエンジニアにとって魅力的なキャリアパスとされています。
その人気の背景には、働き方や仕事の進め方、キャリア形成における独自のメリットが存在します。
自分にとって「楽すぎ」な環境を作りやすい
社内SEは、自社のIT環境を最適化する役割を担っており、その過程で一定の裁量権を与えられることが多くあります。
例えば、非効率な手作業を自動化するツールを自分で選定・導入したり、古くなったシステムを新しい技術で刷新する提案をしたりすることが可能です。
このように、自身の判断で業務プロセスを改善し、より合理的で働きやすい環境、言い方を変えれば「楽すぎな環境」を主体的に構築できる点は、大きな魅力と言えるでしょう。
ただし、「楽」という言葉は、単に仕事が暇だという意味ではありません。
無駄な作業をなくし、本質的な業務に集中できる環境を自ら作り出せる自由度の高さを示唆しています。
納期設定の自由度が高くワークライフバランスが良くなる
社外のクライアントからシステム開発を受注するSIerなどとは異なり、社内SEの顧客は自社の経営層や社員です。
そのため、納期に関しては比較的自由が利きやすい環境だと言えます。
もちろん、プロジェクトには納期が存在しますが、社内の事情を考慮しながら、関係者と直接交渉して現実的なスケジュールを調整しやすいのが特徴です。
無理な納期設定が少ないため、慢性的な長時間労働に陥るリスクが低く、残業時間も少ない傾向にあります。
したがって、プライベートの予定を立てやすく、仕事と生活の調和を図る「ワークライフバランス」を実現しやすくなります。
上流から下流まですべての工程を経験できる
社内SEの仕事は、システム開発の全工程に一気通貫で関われるという特徴があります。
「どのようなシステムがあれば業務が改善されるか」という企画・要件定義といった最上流工程から、設計、開発、導入、そして稼働後の運用・保守、さらにはユーザーからのフィードバックに基づく改善提案まで、すべてを経験できます。
一部分の工程だけを担当することが多いSIerのエンジニアとは異なり、自分が企画したシステムが実際に社内で使われ、事業に貢献していく様子を最後まで見届けられるのは、大きなやりがいにつながるでしょう。
幅広い工程を経験することで、システム全体を俯瞰する視点やプロジェクトマネジメント能力が養われ、エンジニアとして総合的なスキルアップが期待できます。
クライアントが自社の人間なのでプレッシャーが少ない
社内SEが向き合う相手は、同じ会社で働く人たちです。
そのため、社外の顧客とのやり取りで生じるような、過度な緊張感や強いプレッシャーを感じる場面は比較的少ないでしょう。
もちろん、仕事である以上は責任が伴いますが、日頃からコミュニケーションを取っている相手であるため、意思疎通がスムーズに進みやすく、建設的な議論がしやすい環境です。
また、システムを利用するユーザーがすぐ近くにいるため、感謝の言葉を直接聞く機会も多くあります。
「このシステムのおかげで仕事が楽になった」といったフィードバックは、日々の業務のモチベーションを高めてくれるはずです。
社内SEへの転職は難しいものの今ならチャンスがある

転職難易度が高いとされる社内SEですが、現在の市場環境は、転職希望者にとって追い風が吹いていると言えます。
その最大の要因は、多くの企業でDX(デジタルトランスフォーメーション)化が経営上の最重要課題となっていることです。
経済産業省のIT政策実施機関である「IPA」が発表したデータでは、日本企業の約7割がDXに取り組んでおり、その動きは今後さらに加速すると予測されています。
DXを推進するためには、最新のIT技術と自社のビジネスを深く理解し、両者を結びつけて変革を主導できる人材が不可欠です。
まさに、この役割を担うのが社内SEなのです。
従来の「守りのIT」だけでなく、売上向上や新規事業創出に貢献する「攻めのIT」を担う人材として、社内SEの需要は急速に高まっています。
また、クラウドサービスの普及により、自社で大規模なサーバーを持たずにSaaSなどを活用する企業が増えました。
これにより、社内SEの役割もインフラの保守・運用から、各種クラウドサービスの選定・導入やデータ活用といった、より企画・戦略に近い業務へとシフトしています。
このような変化は、新たなスキルセットを持つ人材にとって大きなチャンスとなるでしょう。
難しいと言われる社内SEへの転職を成功させるための戦略
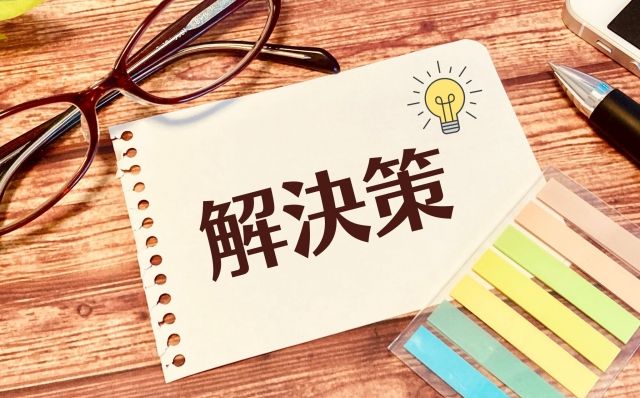
競争の激しい社内SEへの転職を成功させるには、計画的な準備と戦略的なアプローチが欠かせません。
この項目では、自身の市場価値を高め、難しいと言われている社内SEへの転職を成功させるための方法について、詳しく解説していきます。
いきなり社内SEを目指せずにまずは実務経験を積む
IT業界での実務経験が全くない、もしくは乏しい場合、いきなり社内SEのポジションを狙うのは現実的ではありません。
多くの企業が社内SEとしての即戦力を求めているため、まずはITエンジニアとしての基礎体力を身につけることが先決です。
具体的なステップとしては、SIerやSES、自社開発企業などで、システム開発やインフラ構築・運用の実務経験を最低でも2~3年積むことをおすすめします。
プログラミング、データベース、ネットワークといった基本的な技術スキルを習得し、プロジェクトの一連の流れを経験することで、社内SEの選考の土台に乗ることができるでしょう。
遠回りに感じるかもしれませんが、この期間に得た経験は、転職活動だけでなく、社内SEとして働く上でも必ず活きてきます。
下流だけでなく上流工程の仕事も経験しておく
社内SEには、プログラミングやテストといった下流工程のスキルだけでなく、ユーザー部門へのヒアリングから要件をまとめ、システムの仕様を決める上流工程の能力が強く求められます。
開発経験のみの場合、キャリアのどこかで要件定義や基本設計といった業務に携わる機会を作っておくことが非常に重要です。
もし現在の職場で上流工程を経験するチャンスがない場合は、プロジェクトリーダーやマネージャーに積極的にアピールしてみましょう。
顧客との打ち合わせに同席させてもらうだけでも、貴重な経験となります。
面接の場で「ユーザーの要望を形にするために、どのような工夫をしたか」といった具体的なエピソードを語れることは、他の候補者との大きな差別化につながるはずです。
ハードウェアについても詳しくなっておく
社内SEの仕事は、ソフトウェアやシステム開発だけにとどまりません。
社員が業務で使用するPCのセットアップ(キッティング)や、プリンター、ネットワーク機器のトラブルシューティングなど、ハードウェアに関する知識が求められる場面も日常的に発生します。
特に中小企業では、情報システム部門が会社のITに関するあらゆる事柄を一手に引き受ける「一人情シス」のような体制も珍しくありません。
ソフトウェアの知識に加えて、PCのスペック選定や基本的なネットワーク構築に関する知見があれば、対応できる業務の幅が広がり、企業にとって価値の高い人材として評価されやすくなります。
自身のPCを自作したり、自宅のネットワーク環境を構築したりするなど、日頃からハードウェアに触れておくことも有効です。
企業研究を徹底して自分のスキルとマッチする企業を探す
一口に社内SEと言っても、その役割や求められるスキルは、企業の業界、規模、事業フェーズによって大きく異なります。
例えば、製造業と金融業、あるいは大企業とスタートアップでは、使用しているシステムも文化も全く違います。
転職活動を始めるにあたり、まずは自己分析を行い、自身の経験・スキル・強みを棚卸ししましょう。
その上で、徹底的な企業研究が不可欠です。
企業のWebサイトや求人票を読み込み、「どのような事業課題を抱えているのか」「その課題解決のために、どのようなスキルを持つ社内SEを求めているのか」を深く理解してください。
自身のスキルセットと企業のニーズが合致する求人に応募することが、内定への最短ルートです。
自分のやりたいことと、企業が求めていることの重なる部分を見つける作業が、転職成功の鍵を握ります。
社内SE専門の転職エージェントを利用する
社内SEへの転職を成功させる上で、非常に有効な手段が「転職エージェントの活用」です。
中でも、特定の職種に特化したエージェントは、専門性の高いサポートが期待できます。
例えば、「社内SE転職ナビ![]() 」のような社内SE専門の転職エージェントは、一般的なエージェントでは扱っていないような非公開求人を多数保有しています。
」のような社内SE専門の転職エージェントは、一般的なエージェントでは扱っていないような非公開求人を多数保有しています。
企業の事業内容や社風、情報システム部門の体制といった内部情報にも詳しいため、より精度の高いマッチングが可能です。
キャリアアドバイザーは社内SEの業務内容を熟知しており、職務経歴書の添削や面接対策においても、企業のニーズを踏まえた的確なアドバイスを提供してくれるでしょう。
一人で転職活動を進めるよりも、効率的かつ有利に選考を進めることができるはずです。
社内SEへの転職に関するよくある質問

ここでは、社内SEへの転職を検討している方が感じやすい疑問とその回答をまとめました。
転職活動を進める上での参考にしてください。
未経験から社内SEへ転職することは難しい?
結論から言うと、IT業界未経験から直接社内SEへ転職することは非常に難しいのが実情です。
社内SEの求人は、システム開発やインフラ運用などの実務経験者を対象としているケースがほとんどだからです。
まずはSIerや事業会社でITエンジニアとしての実務経験を積み、スキルを身につけてから社内SEを目指すのが一般的なキャリアパスとなります。
ただし、第二新卒などポテンシャルを重視した採用を行う企業も稀に存在するため、可能性がゼロというわけではありません。
なぜ社内SEは勝ち組と言われる?
社内SEが「勝ち組」と称される主な理由は、その働きやすさにあります。
| ワークライフバランス | 納期調整がしやすく、残業が少ない傾向にあるため、プライベートの時間を確保しやすい。 |
| 精神的な安定 | クライアントが自社の社員であるため、過度なプレッシャーが少なく、良好な関係を築きやすい。 |
| 裁量権の大きさ | 自社のIT環境改善のために、主体的に企画・提案できる場面が多い。 |
| 雇用の安定 | 自社システムの根幹を支えるため、景気変動の影響を受けにくく、安定して働きやすい。 |
これらの理由から、多くのITエンジニアにとって理想的な働き方ができる職種と見なされています。
社内SEはやめとけという意見があるのはなぜ?
「社内SEはやめとけ」という意見が見られる背景には、いくつかの理由が考えられます。
最も大きな理由は、これまで述べてきたように、人気が高く求人数が少ないため競争が激しく、転職そのものが非常に難しいという点です。
憧れだけで目指しても、なかなか内定が得られず挫折してしまうケースがあるため、警鐘を鳴らす意味で言われることがあります。
また、企業によっては、情報システム部門の役割が軽視されていたり、予算が少なかったりすることもあります。
その場合、新しい技術に触れる機会が少なく、日々のヘルプデスク業務や雑務に追われてしまい、専門的なスキルが身につきにくいという側面も否定できません。
転職する際は、その企業における社内SEの立ち位置や役割を慎重に見極める必要があります。
まとめ
社内SEへの転職は、その人気の高さと求人の少なさから、確かに簡単な道ではありません。
求められるスキルも広範にわたり、即戦力としての活躍が期待されるため、十分な準備と戦略が必要です。
しかし、DX推進の流れにより、事業を深く理解したIT人材の需要は確実に高まっており、転職市場には大きなチャンスが広がっています。
厳しい競争を勝ち抜くために、「社内SE転職ナビ![]() 」のような社内SE専門の転職エージェントの力を借りることも検討しつつ、ぜひ理想のキャリアを実現してください。
」のような社内SE専門の転職エージェントの力を借りることも検討しつつ、ぜひ理想のキャリアを実現してください。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!