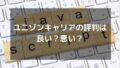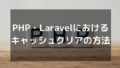デジタル社会の根幹を支えるシステムエンジニア(SE)は、将来性が高く、多くの学生にとって魅力的な職業の一つです。
そのため、SEを目指す上で、「どの大学の、どの学部に進学すれば有利になるのだろうか」と考える高校生や保護者の方も多いのではないでしょうか。
この記事では、システムエンジニアになるために有利となる大学の学部・学科を詳しく解説していきますので、是非参考にしてください。
あなたにベストな
スクール・エージェントが
30秒で一目瞭然!
高性能AIによる無料Web診断
- システムエンジニアになるために有利となる大学の学部
- システムエンジニアを目指すのに大学や学部は関係があるのか
- システムエンジニアを目指す際に最適な大学と学部20選
- 東京大学(理学部:情報科学科)
- 京都大学(工学部:情報学科)
- 東京工業大学(情報理工学院)
- 大阪大学(基礎工学部:情報科学科)
- 東北大学(工学部:電気情報物理工学科)
- 名古屋大学(情報学部:コンピュータ科学科)
- 九州大学(工学部:電気情報工学科)
- 北海道大学(工学部:情報エレクトロニクス学科)
- 筑波大学(情報学群:情報科学類)
- 会津大学(コンピュータ理工学部)
- 早稲田大学(基幹理工学部:情報理工学科)
- 慶應義塾大学(理工学部:情報工学科)
- 東京理科大学(理工学部:情報科学科)
- 明治大学(総合数理学部:先端メディアサイエンス学科)
- 同志社大学(理工学部:情報システムデザイン学科)
- 立命館大学(情報理工学部)
- 中央大学(理工学部:情報工学科)
- 法政大学(情報科学部:コンピュータ科学科)
- 芝浦工業大学(工学部:情報工学科)
- 東京電機大学(システムデザイン工学部:情報システム工学科)
- システムエンジニアになるために大学へ通うメリット
- システムエンジニアになるために大学へ通うデメリット
- まとめ
システムエンジニアになるために有利となる大学の学部

システムエンジニアを目指す上で、最も直接的に有利となるのは、コンピュータサイエンスの基礎から応用までを体系的に学べる学部です。
具体的には、以下のような学部・学科が挙げられます。
- 情報工学部
- 情報科学部
- 理工学部(情報科学科、電子情報工学科など)
- 工学部(情報通信工学科、システム工学科など)
- 総合情報学部
- メディア学部
これらの学部では、プログラミング言語の習得はもちろん、システム開発の土台となる重要な知識を学びます。
例えば、コンピュータがどのように動作するのかを理解する「コンピュータアーキテクチャ」、効率的なプログラムを作成するための「アルゴリズムとデータ構造」、情報を安全にやり取りするための「ネットワーク技術」、大量のデータを管理する「データベース」などです。
これらの知識は、単にコードが書けるだけでなく、高品質で堅牢なシステムを設計・開発できるエンジニアになるための基礎体力となります。
大学でこれらの学問を深く学ぶことは、将来のキャリアにおいて大きなアドバンテージとなるでしょう。
システムエンジニアを目指すのに大学や学部は関係があるのか

結論から言うと、システムエンジニアになるために特定の大学や学部を卒業することが必須条件ではありません。
文系学部出身者や、専門学校、独学でスキルを身につけて活躍しているエンジニアも数多く存在します。
IT業界は実力主義の側面が強く、学歴よりも個人の技術力や問題解決能力が重視される傾向にあるからです。
しかし、大学の情報系学部で学ぶことには大きなメリットがあるのも事実です。
新卒採用の場において、情報系の学部を卒業していることは「ITに関する基礎的な素養がある」という客観的な証明になります。
企業側も、入社後の教育コストを抑えられると判断し、ポテンシャルを評価しやすくなるでしょう。
特に、大手企業や研究開発職を目指す場合は、応募条件として「情報系の学士以上の学位」が求められることも少なくありません。
したがって、「関係ないとは言えないが、絶対ではない。ただし、情報系の学部で学ぶ方が有利なスタートを切れる可能性が高い」というのが実情だと言えるでしょう。
システムエンジニアを目指す際に最適な大学と学部20選

システムエンジニアになるために大学へ通うメリット

システムエンジニアへの道は大学進学だけではありませんが、大学で学ぶことには他では得がたい多くのメリットが存在します。
ここでは、大学へ通うことが将来のキャリアにどう繋がるのか、具体的な利点を解説します。
企業から「システムエンジニアとしての素養がある」と判断されやすい
新卒採用の現場では、応募者がまだ実務経験を持っていないため、ポテンシャルが重視されます。
情報系の学部で学んだ経験は、プログラミングやコンピュータサイエンスに関する基礎知識を持っていることの客観的な証明となります。
企業側は、論理的思考力や学習意欲の高さを評価し、「入社後にエンジニアとして成長してくれるだろう」という期待を持ちやすくなるのです。
これは、特に人気企業や大手企業の選考において、書類選考や一次面接を通過する上で有利に働くでしょう。
時間をかけて体系的に学習できる
大学の4年間という時間は、システムエンジニアに必要な知識を腰を据えて学ぶための貴重な期間です。
大学の場合、なぜその技術が必要なのか、どのような仕組みで動いているのかといった、より本質的なコンピュータサイエンスの基礎理論から体系的に学べます。
この基礎知識は、新しい技術が登場した際にいち早く理解し応用する力や、複雑な問題を解決する際の土台となり、長く活躍し続けるエンジニアになるための重要な資産となるのです。
就職の選択肢が広がる
大卒という学歴、特に情報系の学位を持っていることで、就職活動における選択肢は大きく広がります。
大手IT企業やメーカー、金融機関のIT部門など、新卒採用の応募条件を「大卒以上」としている企業は少なくありません。
また、大学には企業からの推薦制度があったり、OB・OG訪問を通じてリアルな情報を得やすかったりといったメリットもあります。
キャリアセンターによる就職支援も充実しており、多様なキャリアパスの中から自分に最適な道を見つけやすい環境が整っていると言えるでしょう。
システムエンジニアになるために大学へ通うデメリット
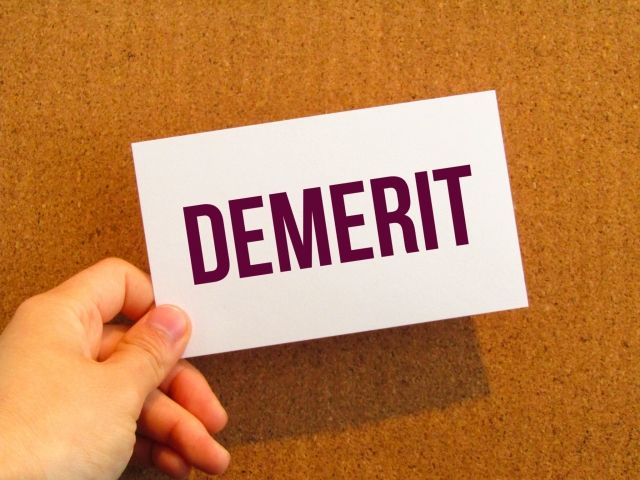
大学進学には多くのメリットがある一方で、時間や費用、学習内容の面で考慮すべきデメリットも存在します。
これらの点を理解した上で、自分にとって最適な道を選択することが重要です。
大学に行かなくてもシステムエンジニアにはなれる
最も大きな点は、大学を卒業しなくてもシステムエンジニアとして就職し、成功することは十分に可能であるという事実です。
IT業界は実力主義であり、最終的には個人のスキルが評価されます。
近年では、質の高いオンライン教材やプログラミングスクールが充実しており、実践的なスキルを短期間で集中的に学ぶことができます。
大学に通わずにいち早く実務経験を積むことで、同年代の大卒者よりも早くキャリアをスタートさせるという選択肢も現実的です。
学費がかかる
大学に通うには、当然ながら高額な学費が必要です。
4年間の学費の総額は、国公立大学でおよそ250万円、私立大学の理系学部では500万円以上になることも珍しくありません。
これに加えて、一人暮らしをする場合は生活費もかかります。
経済的な負担は決して軽くはなく、奨学金を利用する場合は卒業後に返済の義務が生じることも考慮に入れる必要があります。
これだけの費用と時間をかけるのならば、より安く、より短期間でスキルを習得できるプログラミングスクールへの投資に充てるという考え方もあるでしょう。
大学で学んだ内容が役に立つとは限らない
IT業界は技術の進化が非常に速く、「ドッグイヤー」とも呼ばれる世界です。
そのため、大学のカリキュラムが必ずしも最新のトレンドを反映しているとは限りません。
例えば、大学1年生の時に学んだプログラミング言語やフレームワークが、卒業する頃にはすでに古くなっている(陳腐化している)という事態も起こり得ます。
大学で学ぶ基礎理論は普遍的な価値を持ちますが、現場で求められる実践的な最新技術については、常に自分でアンテナを張り、学習し続ける姿勢が不可欠であることを理解しておく必要があります。
まとめ
システムエンジニアを目指す上で、大学の情報系学部で学ぶことは、専門知識を体系的に習得し、就職活動を有利に進めるための有効な選択肢です。
特に、コンピュータサイエンスの基礎をしっかりと固めることは、将来長く活躍するための強固な土台となるでしょう。
一方で、大学に行かずともエンジニアになる道は開かれています。
大学進学のメリットとデメリットをよく理解した上で、自身の目標や状況に合わせた最適な方法を選択してください。
あなたにベストな
スクール・エージェントが
30秒で一目瞭然!
高性能AIによる無料Web診断


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!