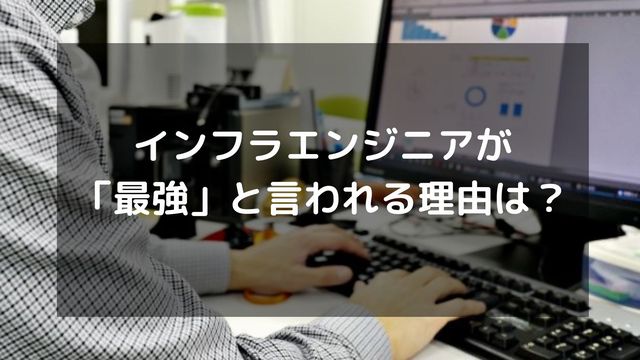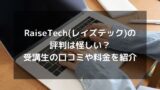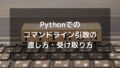需要の高さや将来性から、そんな言葉を耳にしたことがあるかもしれません。
インフラエンジニアとして、ITシステムの根幹を支える重要な役割は確かに大きな魅力です。
しかしその一方で、「夜勤が大変そう」「責任が重くてきつい」といったネガティブな評判も存在し、本当の姿が見えにくいと感じている方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、なぜインフラエンジニアが「最強」と言われるのか、その具体的な理由を徹底解説しつつ、知っておくべきデメリットや仕事の厳しさも紹介していきますので、是非参考にしてください。
 |
|


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!
インフラエンジニアが最強と言われる6つの理由

IT業界において、なぜインフラエンジニアは「最強」とまで言われることがあるのでしょうか。
それは、他の職種にはない「独自の強み」や「安定性」を備えているからです。
ここでは、インフラエンジニアが最強と言われる根拠となる6つの理由を詳しく解説していきます。
未経験からでも目指しやすい職種
インフラエンジニアは、専門性が高い職種でありながら、未経験からでもキャリアをスタートさせやすいという大きな特徴があります。
その理由の一つは、業務内容が段階的になっていることです。
最初はシステムの稼働状況をチェックする「監視」や、マニュアルに沿って対応する「運用・保守」といった業務から始めることが多く、実務を通じて着実に知識とスキルを身につけていけます。
多くの企業では、未経験者向けの研修制度を充実させており、入社後にサーバーやネットワークの基礎から学べる環境が整っています。
そのため、プログラミングのように複雑なコードを最初から書く必要がなく、IT業界への入り口として非常に門戸が広い職種なのです。
強い意欲さえあれば、全くの異業種からでも挑戦できる点は、大きな魅力といえるでしょう。
インフラがなければシステムは動かない
インフラエンジニアが担うサーバーやネットワークといったITインフラは、あらゆるWebサイトやアプリケーション、企業の業務システムが動作するための土台です。
どれだけ優れたシステムが開発されても、それを支える安定したインフラがなければ、サービスとして成立しません。
電気や水道のように、現代社会においてITインフラは必要不可欠な存在なのです。
現在、企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)はますます加速しており、クラウド化やデータ活用が事業成長の鍵を握っています。
それに伴い、システムの基盤を支えるインフラエンジニアの重要性はさらに高まっています。
経済産業省が警鐘を鳴らす「2025年の崖」問題でも指摘されている通り、IT人材の不足は深刻であり、社会の根幹を支えるインフラエンジニアの需要が尽きることは考えにくいでしょう。
この「社会的な重要性」と「代替不可能性」が、最強と言われる大きな所以です。
基本的に残業が発生しにくい
インフラエンジニアの主な業務は、システムの安定稼働を守ることです。
そのため、24時間365日のシフト制で監視・運用を行う現場が多く、個人の勤務時間はきっちりと管理されている傾向にあります。
自分の担当時間が終われば、次の担当者に業務を引き継ぐため、突発的なトラブルがない限りは定時で退社しやすい環境が整っているのです。
もちろん、これは平常時の話であり、後述するような緊急対応が発生することもあります。
しかし、アプリケーション開発のように、納期間近になると連日深夜まで残業が続くといった働き方とは異なります。
ワークライフバランスを重視したい人にとって、比較的スケジュール管理がしやすく、プライベートの時間を確保しやすい点は、インフラエンジニアの大きなメリットといえるでしょう。
習得したスキルを長く使える
IT業界は技術の流行り廃りが激しい世界ですが、インフラエンジニアが扱う基礎技術は比較的変化が緩やかで、一度習得したスキルが陳腐化しにくいという強みがあります。
サーバーのOS(Linuxなど)や、ネットワークの仕組み(TCP/IPなど)といった根幹的な知識は、10年後、20年後も通用する普遍的なスキルです。
近年ではAWS(Amazon Web Services)などのクラウド技術が主流になっていますが、これも従来のオンプレミス環境で培われたインフラの基礎知識があってこそ、深く理解し、応用することができます。
新しい技術が登場しても、これまでの知識を土台として積み上げていけるため、継続的に学習すれば、長く第一線で活躍し続けることが可能です。
流行に左右されにくい安定したスキルセットを構築できることは、長期的なキャリアを考える上で非常に有利に働くでしょう。
AIに仕事を奪われにくい
「AIに仕事を奪われる」という議論が盛んですが、インフラエンジニアのコア業務はAIによる代替が難しい領域だと考えられています。
確かに、システムの監視や定型的な運用作業の一部は、AIによって自動化が進んでいます。
しかし、それはインフラエンジニアの仕事がなくなることを意味するわけではありません。
むしろ、AIを「活用する側」に回ることで、より高度で創造的な業務に集中できるようになるのです。
例えば、以下のような業務はAIには困難です。
| 複雑なシステムの全体設計 | ビジネス要件を理解し、可用性、拡張性、セキュリティなどを考慮した最適なインフラをゼロから設計する。 |
| 未知の障害対応 | 前例のないトラブルが発生した際に、原因を特定し、複雑な要素を考慮しながら復旧プランを立案・実行する。 |
| 高度なセキュリティ対策 | 巧妙化するサイバー攻撃の手口を予測し、戦略的な防御策を講じる。 |
| 関係各所とのコミュニケーション | 他部署やクライアントと折衝し、技術的な内容を分かりやすく説明して合意形成を図る。 |
これらの業務には、論理的思考力や仮説検証能力、そしてコミュニケーション能力といった、人間にしか持ち得ない高度なスキルが求められます。
定型業務をAIに任せ、より付加価値の高い仕事にシフトできるインフラエンジニアは、今後さらに市場価値を高めていくでしょう。
キャリアパスの選択肢が広い
インフラエンジニアとして経験を積んだ後には、非常に多様なキャリアパスが広がっています。
ITインフラに関する深い知識は、様々なIT職種の土台となるため、自分の興味や適性に合わせて柔軟にキャリアを築いていくことが可能です。
具体的なキャリアパスの例としては、以下のようなものが挙げられます。
- スペシャリスト:特定分野の技術を極める専門家
- ITアーキテクト:企業全体のIT戦略に基づき、最適なシステム基盤を設計する
- プロジェクトマネージャー:インフラ構築プロジェクト全体の責任者として、進捗や予算、人材を管理する
- ITコンサルタント:企業の経営課題をITインフラの観点から解決策を提案する
- フルスタックエンジニア:インフラからアプリケーション開発まで幅広く対応する
このように、一つの道に縛られることなく、様々なキャリアを選択できる自由度の高さも、インフラエンジニアが「最強」と言われる一因です。
最強と言われるインフラエンジニアにもデメリットはある

「最強」と言われるインフラエンジニアですが、当然ながら良い面ばかりではありません。
良いところばかりといったイメージの裏にある、知っておくべきデメリットについても正直に解説します。
残業は少ないものの突発的な呼び出しがある
平常時の残業は少ない傾向にありますが、インフラエンジニアの宿命ともいえるのが、突発的な障害対応です。
システムは24時間365日動き続けているため、深夜や休日に関わらず、障害が発生すれば緊急で対応にあたる必要があります。
オンコール当番として、勤務時間外でも常に連絡が取れるように待機していなければならない制度を設けている企業も少なくありません。
プライベートな時間であっても、いつ呼び出されるかわからないという緊張感は、精神的な負担になる可能性があるでしょう。
夜間業務もあるので生活リズムが狂いやすい
システムのメンテナンスやアップデート作業は、ユーザーへの影響を最小限に抑えるため、多くの人が利用していない夜間に行われるのが一般的です。
そのため、インフラエンジニアは夜勤やシフト制勤務になることが珍しくありません。
昼夜逆転の生活が続くと、生活リズムが乱れて体調を崩しやすくなることもあります。
特に、日勤と夜勤が混在する不規則なシフトの場合は、自己管理能力が強く求められるでしょう。
家族や友人との時間を合わせにくいというデメリットも考えられます。
システムの土台となるインフラを支えるためプレッシャーが大きい
インフラの停止は、企業のビジネス活動や社会の機能に直接的なダメージを与えかねません。
例えば、ECサイトのサーバーがダウンすれば、その間の売上はゼロになります。
金融システムのインフラに障害が起きれば、社会的なパニックを引き起こす可能性すらあります。
このように、社会インフラを支えるという重要な役割を担っているからこそ、そのプレッシャーは計り知れません。
「絶対に止めてはいけない」という重圧の中で、常に冷静かつ正確な作業が求められるため、精神的にタフでなければ務まらない仕事だといえるでしょう。
最強のインフラエンジニアになれる素質のある人

インフラエンジニアは誰にでも務まる仕事ではありませんが、特定の素質を持つ人にとっては、まさに天職となり得ます。
ここでは、どのような人が「最強のインフラエンジニア」になれるポテンシャルを秘めているのか、その特徴を解説します。
ストレスに強い
インフラエンジニアは、前述の通り、突発的な障害対応や大きなプレッシャーの中で仕事をすることがあります。
予期せぬトラブルが発生した際にパニックに陥ることなく、冷静に原因を分析し、論理的に対処法を導き出す必要があるのです。
このような緊迫した状況でも、落ち着いてパフォーマンスを発揮できる精神的な強靭さ、すなわちストレス耐性は、最も重要な素質の一つといえるでしょう。
困難な状況を楽しめるくらいの気概がある人には、特におすすめできます。
単調なルーチンワークを苦に感じない
インフラエンジニアの仕事には、システムの正常性を日々確認する監視業務や、定期的なバックアップ作業、地道な設定作業など、一見すると単調なルーチンワークが多く含まれます。
これらの作業は、システムの安定稼働を維持するための非常に重要な業務です。
派手さはありませんが、決められた手順を正確に、そして根気強く続けられる真面目さや集中力が求められます。
コツコツと地道な作業を積み重ねることにやりがいを感じられる人は、インフラエンジニアとしての適性が高いといえます。
誰かをサポートするのが好き
インフラエンジニアは、アプリケーションを開発するエンジニアや、システムを利用するエンドユーザーを、ITインフラという土台から支える「縁の下の力持ち」です。
自分が表舞台に立つことよりも、他の誰かが快適に仕事ができる環境を整えることに喜びを感じる人は、この仕事に大きなやりがいを見出すことができるでしょう。
他者への貢献意欲や、困っている人を助けたいという気持ちが、日々の業務のモチベーションに繋がります。
未経験だけどエンジニアになりたいという気持ちが強い
現時点でのスキルや知識も大切ですが、それ以上に重要なのが「エンジニアになりたい」という強い熱意です。
ITインフラの世界は常に進化しており、新しい技術が次々と登場します。
そのため、現状に満足することなく、常に学び続ける姿勢が不可欠です。
未経験であっても、この強い学習意欲と向上心があれば、入社後にいくらでもスキルを伸ばしていくことが可能です。
経歴や学歴以上に、未来へのポテンシャルが重視される職種だといえるでしょう。
「素質のある人」に当てはまれば最強のインフラエンジニアになれる!

ここまで、インフラエンジニアが「最強」と言われる理由、その裏にあるデメリット、そして向いている人の素質について解説してきました。
もし、「ストレスに強い」「地道な作業が好き」「誰かを支えたい」「エンジニアになりたい気持ちが強い」といった素質に一つでも当てはまるのであれば、インフラエンジニアとして大きく活躍できる可能性があります。
デメリットとして挙げた夜間業務やプレッシャーも、あなたにとっては「集中できる環境」や「やりがいのある責任」と捉えられるかもしれません。
未経験からでも挑戦でき、一度身につけたスキルで長く社会に貢献できるインフラエンジニアは、まさに適性のある人にとって「最強」の職業です。
もし少しでも興味が湧いたなら、次のステップとして、具体的な学習を検討してみてはいかがでしょうか。
未経験からインフラエンジニアを目指す人におすすめのプログラミングスクール3選

未経験からインフラエンジニアを目指す場合、専門のスクールで体系的に知識を学び、転職サポートを受けるのが最も確実な道です。
ここでは、特に評判の高いインフラエンジニア関連の3つのスクールを紹介します。
ウズウズカレッジ
ウズウズカレッジは、20代の第二新卒や既卒、フリーターの就職支援に特化したスクールです。
特にインフラエンジニア向けの「CCNAコース」が人気で、ネットワークの基礎から実践までを学ぶことができます。
個別サポートが非常に手厚く、一人ひとりの学習進捗やキャリアプランに合わせた指導を受けられるのが大きな特徴です。
就職内定率も高く、書類選考や面接対策まで徹底的にサポートしてくれるため、安心して転職活動に臨めるでしょう。
RaiseTech
RaiseTechは、「稼ぐための技術を教える」をコンセプトに掲げる、現場主義のスクールです。
講師はすべて現役のエンジニアであり、教科書的な知識だけでなく、現場で本当に役立つ実践的なスキルを学ぶことができます。
インフラ関連の中でも、特にクラウド技術である「AWS(Amazon Web Services)」を網羅的に学べるコースが特徴的で、現代のインフラエンジニアに必須のクラウドスキルを習得したい人に最適です。
半永久的な質問対応や転職サポートなど、卒業後の支援が充実している点も魅力です。
ササエル
ササエルは、インフラエンジニアに特化したカリキュラムを用意している、比較的新しいスクールです。
「クラウドとは」「ネットワークの仕組み」「サーバーとは」「OSとは」といったように、インフラエンジニアにとって欠かせない意識・スキルを学ぶことができます。
なおササエルでは、「1人につき1台、VPS(仮想サーバー)を提供する」という、他のプログラミングスクールにはない試みを実践しています。
まとめ
以上、インフラエンジニアが「最強」と言われる理由を、需要の高さ、スキルの汎用性、キャリアパスの広さといった多角的な視点から解説しました。
インフラエンジニアは、社会に不可欠なITインフラを支える、非常に重要でやりがいのある仕事です。
その一方で、大きな責任とプレッシャーが伴うことも事実です。
この記事で紹介した「最強の理由」と「デメリット」、そして「求められる素質」を天秤にかけ、自分にとって本当に「最強」の職業となり得るのか、じっくりと見極めることが重要でしょう。

【スクール選びで後悔したくない方へ】
4年連続で人気No.1となっている「RUNTEQ」は、当ブログで調査した数多くのスクールの中でも大変おすすめです。なぜ選ばれ続けているのか、 その理由や受講生の評判については、以下の記事で詳しくまとめています。
※直接公式サイトを確認したい方はRUNTEQ公式サイトからどうぞ。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!