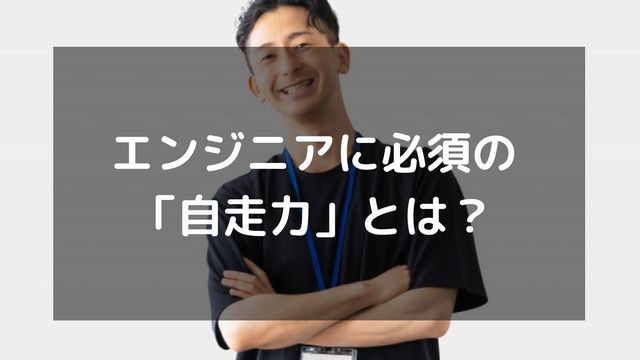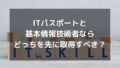「ITエンジニアの求人情報」や「現場で求められるエンジニア像」などで、必ずと言っていいほど登場するキーワードが「自走力」です。
多くの企業が採用基準としてこの能力を重視しており、エンジニアとしてキャリアを築いていく上で、自走力はもはや技術力と同じくらい重要なスキルとなっています。
しかし、「自走力」という言葉は非常に抽象的で、「具体的に何を指すのか」「どうすれば身につけられるのか」「面接でどうアピールすればいいのか」といった点で、悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、エンジニアに求められる「自走力」の本当の意味を解説しつつ、自走力を鍛える方法や面接で効果的にアピールする方法などについて紹介していきます。
 |
|

【スクール選びで後悔したくない方へ】
4年連続で人気No.1となっている「RUNTEQ」は、当ブログで調査した数多くのスクールの中でも大変おすすめです。なぜ選ばれ続けているのか、 その理由や受講生の評判については、以下の記事で詳しくまとめています。
※直接公式サイトを確認したい方はRUNTEQ公式サイトからどうぞ。
エンジニアにおける「自走力」とは何か?

まず、「自走力」という言葉の意味を正しく理解することが重要です。
エンジニアの世界における自走力とは、単に「一人で黙々と作業ができる能力」や「指示されたことを正確にこなす能力」を指すのではありません。
より本質的には、「自ら課題を発見し、その解決に向けて何をすべきかを考え、周囲を巻き込みながら主体的に行動できる能力」と定義できます。
指示を待つのではなく、常に「目的は何か」「もっと良い方法はないか」を考え、未知のエラーや問題に直面した際には、他責にすることなく、自分で情報収集や試行錯誤を重ねて解決の糸口を見つけ出そうとする姿勢。
こうした一連の主体的な行動こそが、エンジニアに求められる「自走力」の正体です。
なぜ今、エンジニアに自走力が求められるのか?

かつてのエンジニアは、「仕様書に基づいて淡々と正確に決められたものを作る」という働き方も一般的でした。
しかし、現代の開発現場ではそうではなく、自走力が強く求められるようになっています。
なぜ、これほどまでに自走力が重視されるようになったのか?
その理由を解説していきます。
技術の変化が速く常に学び続ける必要があるから
IT業界、特にWeb技術の進化のスピードは驚異的です。
数年前に主流だった技術が、あっという間に時代遅れになることも珍しくありません。
このような環境では、会社が研修を用意してくれるのを待っているだけでは、すぐにエンジニアとしての市場価値が失われてしまいます。
自走力のあるエンジニアは、常に技術のトレンドを追いかけ、自分に必要なスキルは何かを判断し、業務時間外でも自主的に学習を進めます。
この継続的な自己研鑽の姿勢がなければ、変化の速い業界で生き残っていくことは困難なのです。
チーム全体の生産性を向上させるから
現代のソフトウェア開発は、ほとんどがチームで行われます。
そして、チームメンバー一人ひとりが自走力を持っていると、プロジェクトは非常にスムーズに進行します。
例えば、誰かがエラーで詰まってしまった時、自走力のあるメンバーはまず自分で解決を試みます。
それでも解決しない場合は、「何を、どこまで、どう試したか」を明確にしてから他のメンバーに相談するため、問題の共有と解決が迅速に進みます。
逆に、指示待ちのメンバーばかりだと、リーダーが細かく指示を出す必要があり、チーム全体のスピードが著しく低下してしまうでしょう。
リモートワークという働き方が主流になったから
リモートワークの普及も、自走力の重要性を高める大きな要因となりました。
オフィスにいれば、気軽に隣の席の同僚に質問したり、様子を察してもらえたりしたかもしれません。
しかし、リモート環境では、各自が責任を持って自律的に業務を進めることが大前提となります。
進捗が遅れていても自分から発信しなければ誰も気づけませんし、課題に直面しても、まずは自力で解決策を探す姿勢がなければ、業務が停滞してしまいます。
自走力は、場所を選ばずに成果を出すための必須スキルになったのです。
自走力のあるエンジニア・ないエンジニアの特徴

自走力の有無は、日々の業務における具体的な行動の違いとして現れます。
以下の表で、両者の特徴を比較してみましょう。
| 自走力のあるエンジニアの行動 | 自走力のないエンジニアの行動 | |
|---|---|---|
| 仕事の進め方 | タスクの目的や背景を理解し、より良い方法を提案する。 | 指示された範囲のことだけを、指示された通りに行う。 |
| 問題発生時 | まずエラーメッセージを読み、自分で調査・試行錯誤を行う。 | すぐに「わかりません」「できません」と他者に答えを求める。 |
| 情報収集 | 公式ドキュメントや技術ブログを日常的に読み、能動的に学習する。 | 研修や上司からの指示がない限り、新しいことを学ばない。 |
| コミュニケーション | 自分の意見や進捗状況を、積極的にチームへ共有・発信する。 | 問題が起きるまで報告・連絡・相談を怠りがち。 |
エンジニアとしての自走力を鍛える5つの方法

自走力は、生まれ持った才能ではなく、日々の意識と実践によって後天的に鍛えることができるスキルです。
ここでは、そのための具体的な方法を5つ紹介します。
まず自分で調べる・試す癖をつける
「何かあればまず自分で調べる・試す」というのは、最も基本的かつ重要な習慣です。
エラーや不明点に遭遇した際、すぐに誰かに質問するのではなく、最低でも「一定時間」は自分で徹底的に調べて試行錯誤するというルールを自分に課してみてください。
なお、「一定時間」については、ケースバイケースです。
調べればわかりそうなことならば、1~2時間かけてでも調べるべきでしょう。
逆に、その会社独特のレギュレーションに関連するような問題であれば、多少調べてわからなければ、先輩や上司に聞いた方が早いです。
注意すべきなのは、「自走力の高さ = 質問しないこと」ではない、という点です。
いくら自己解決したいからといって、同じ疑問に丸一日つかまっているような状態になれば、それだけ開発が遅れ、結果としてチームに迷惑をかけてしまいます。
課題によって、「これくらい調べてわからなければ、質問した方がよい」というラインがあります。
このラインは、日々課題に対して試行錯誤しているうちに段々とわかってきますので、とにかく多くの課題と向き合い、できる限り自己解決するという意識を持って立ち向かってください。
「なぜ?」を繰り返し、目的意識を持つ
与えられたタスクをただの作業としてこなすのではなく、常に「なぜこの機能が必要なのか?」「このタスクの目的は何か?」と、その背景にある目的を考える癖をつけましょう。
目的を理解することで、単に言われた通りに作るのではなく、「こちらの実装の方が、本来の目的に合っているのではないか」といった、より付加価値の高い提案ができるようになります。
問題解決のプロセスを確立する
闇雲に試行錯誤するのではなく、自分なりの問題解決の型(プロセス)を持つことが、自走力を高める上で非常に有効です。
例えば、エラーが発生した時のプロセスとしては以下の通りです。
- 現状把握:エラーメッセージを正確に読む。いつから、何をしたら発生したのかを切り分ける。
- 仮説立案:「おそらく、ここの変数の値が原因ではないか」といった仮説を立てる。
- 検証:仮説を証明するために、ログを出力したり、コードを部分的に変更したりして試す。
- 考察:検証結果がどうだったか、仮説は正しかったかを考察し、次の仮説につなげる。
こういったアプローチを繰り返すことで、あらゆる問題に対応できる論理的思考力が養われます。
それが自走力に繋がるのです。
インプットだけでなくアウトプットを習慣化する
新しい技術を学んだだけで満足せず、その知識を使って何かを作ってみたり、学んだことを自分の言葉で技術ブログにまとめたりする習慣は、自走力を飛躍的に高めます。
アウトプットを前提とすることで、インプットの質が格段に向上します。
他人に説明できるレベルまで理解しようと努めるため、知識がより深く定着するのです。
また、GitHubで個人開発のプロジェクトを公開することも、スキルの証明と学習意欲のアピールに繋がります。
小さなことでも当事者意識を持つ
- チームで使っているツールの設定が少し使いにくい
- ドキュメントの一部が古いままになっている
こういった小さな問題に気づいた際に、他人事として放置しないことも重要です。
「自分が改善案を提案してみよう」「自分がドキュメントを修正しよう」と、常に当事者意識を持って行動を起こす経験を積み重ねることで、より大きな課題に対しても主体的に取り組む姿勢が自然と身についていきます。
【例文あり】面接で自走力を効果的にアピールする方法

自走力は目に見えないスキルだからこそ、採用面接では、具体的なエピソードを交えてアピールする必要があります。
単に「私には自走力があります」と言うだけでは、何の説得力もありません。
アピールする際は、「STARメソッド」を意識すると話が伝わりやすくなります。
STARメソッドとは、経験や行動を、「状況(Situation)」「課題(Task)」「行動(Action)」「結果(Result)」の順に整理して伝える、面接や自己PRに使える話し方の型です。
| S(Situation) | どのようなプロジェクトで、どんな課題があったか |
| T(Task) | その状況で、自分が何をすべきだったか |
| A(Action) | 課題解決のために、具体的にどう考え、どう行動したか |
| R(Result) | その行動によって、どのような成果が得られたか |
STARメソッドを活用した、面接でのアピール例文としては以下の通りです。
前職で、担当していた機能のテストコードが不足しており、品質が担保されていないという課題がありました(S)。
私は、品質向上と今後の開発効率化のために、テストカバレッジを向上させるべきだと考えました(T)。
そこで、まず独学でテストフレームワークのキャッチアップを行い、既存のコードに対するテストを自主的に追加しました。
さらに、その過程で得た知見をチーム内に共有し、テストコードを書く文化を根付かせるための勉強会を主催しました(A)。
結果として、担当機能のバグ発生率を30%削減し、チーム全体の開発速度の向上にも貢献することができました(R)。
自身の自走力をアピールする際に、上記のような例文を是非活用してください。
まとめ
以上、現代のエンジニアにとって不可欠なスキルである「自走力」について、その本質から具体的な鍛え方、そして面接でのアピール方法までを詳しく解説してきました。
自走力は、一朝一夕で身につくものではありません。
しかし、この記事で紹介したような日々の小さな積み重ねによって、確実に鍛えることができる能力ですので、これからエンジニアを目指す方も、すでにエンジニアとして働いている方も、是非意識して鍛えるようにしてください。

【スクール選びで後悔したくない方へ】
4年連続で人気No.1となっている「RUNTEQ」は、当ブログで調査した数多くのスクールの中でも大変おすすめです。なぜ選ばれ続けているのか、 その理由や受講生の評判については、以下の記事で詳しくまとめています。
※直接公式サイトを確認したい方はRUNTEQ公式サイトからどうぞ。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!