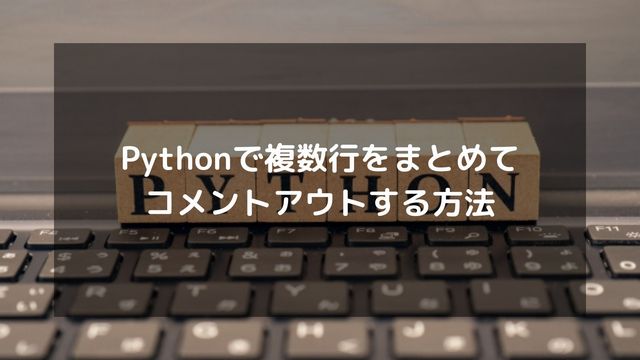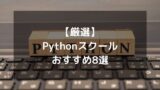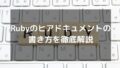Pythonでコードを書いていると、デバッグのために一部の処理を一時的に実行しないようにしたり、古いコードを参考のために残しておいたりしたい場面がよくあります。
一行ずつ#を付けてコメントアウトするのは、行数が多くなると非常に面倒ですよね。
そんなとき、複数行を一度にコメントアウトする方法を知っていると、開発効率が格段に向上します。
この記事では、Pythonで複数行をまとめてコメントアウトするための、実用的で簡単な2つの方法を、それぞれのメリットや注意点とともにわかりやすく解説していきます。
数あるスクールを徹底比較した結果、未経験から本気でプロを目指すなら、今の選択肢は「RUNTEQ」一択です。
- ✅ 給付金で実質13万円〜の圧倒的なコスパ
- ✅ 現場で通用する「本物の開発力」が身につく
- ✅ 受講生コミュニティの活発さが業界No.1
※無理な勧誘は一切ありません。相談だけでも価値があります。
【Pythonでまとめてコメントアウトする方法①】エディタのショートカットキー
最も簡単で、プロの開発現場でも一般的に使われているのが、使っているコードエディタ(VS CodeやPyCharmなど)が持つショートカット機能を利用する方法です。
ショートカットキーの使い方と解除
使い方は非常に直感的です。
- コメントアウトしたい複数行をマウスで選択します。
- 以下のショートカットキーを押します。
- Windows / Linux:
Ctrl+/ - Mac:
Cmd+/
- Windows / Linux:
これだけで、選択したすべての行の先頭に#が付き、まとめてコメントアウトできます。
# ショートカットキーを押す前のコード
print("処理A")
# print("デバッグ用の処理")
# print("これも今は不要")
print("処理B")
例えば、2行目と3行目を選択してショートカットキーを押すと、以下のようになります。
# ショートカットキーを押した後のコード
print("処理A")
# # print("デバッグ用の処理")
# # print("これも今は不要")
print("処理B")
コメントアウトを解除したい(元に戻したい)場合も、同じように対象の行を選択して、同じショートカットキー(Ctrl + / or Cmd + /)を押すだけです。
コメント化と非コメント化を簡単にトグル(切り替え)できます。
この方法のメリット
各行が
#で始まるため、Pythonの構文として完全に正しいコメントになります。同じキー操作でコメント化と解除を素早く切り替えられるため、デバッグ作業が非常にスムーズです。
VS Code、PyCharm、Sublime Text、Atomなど、現代の主要なコードエディタのほとんどがこのショートカットに対応しています。
特別な理由がない限り、複数行のコメントアウトにはこの方法を使うのがベストプラクティスと言えるでしょう。
【Pythonでまとめてコメントアウトする方法②】三重クォート
もう一つの方法として、Pythonの「複数行文字列リテラル」を、ブロックコメントのように使うテクニックがあります。
三重クォートの使い方
コメントアウトしたい範囲の先頭を"""(ダブルクォート3つ)または'''(シングルクォート3つ)で囲み、末尾も同じもので閉じます。
print("処理Aは実行されます")
"""
print("この部分は実行されません")
a = 1 + 2
print(a)
"""
print("処理Bは実行されます")
実行結果は以下の通りです。
処理Aは実行されます
処理Bは実行されます
このように、"""で囲まれたブロック内のコードは実行されなくなります。
注意点は「厳密にはコメントではない」という点
この方法は手軽に見えますが、一つ重要な注意点があります。
それは、三重クォートで囲まれた部分は、技術的には「コメント」ではなく、「どこにも代入されていない単なる文字列」として扱われるという点です。
Pythonでは、この文字列は構文上は文字列リテラルとして扱われます。
処理系によっては最適化で除去されることもありますが、いずれにしても#を使った本当のコメントとは内部的な扱いが異なります。
特に、関数やクラス、モジュールの先頭にこの形式で記述すると、「ドキュメンテーション文字列(docstring)」という特殊な意味を持つようになります。
def sample_func():
"""
この関数はサンプルです。
引数はありません。
"""
print("関数が実行されました")
# __doc__属性でドキュメンテーション文字列を参照できる
print(sample_func.__doc__)
実行結果は以下の通りです。
この関数はサンプルです。
引数はありません。
このように、本来の用途とは異なる使い方であるため、チーム開発の現場などでは混乱を招く可能性も否定できません。
どちらの方法を使うべき?
結論から言うと、基本的には常に「エディタのショートカットキー」を使うことを強く推奨します。
| 比較項目 | エディタのショートカット (#) |
三重クォート (""") |
|---|---|---|
| 意味 | 正しいコメント | 文字列リテラル(コメントではない) |
| 動作 | 確実・安全 | docstringになるなど副作用の可能性あり |
| 使いやすさ | ショートカットで一瞬 | 手入力で囲む必要がある |
| 推奨度 | ◎(非常に推奨) | △(限定的な利用に留めるべき) |
三重クォートによるコメントアウトは、Pythonの言語仕様をハックした一時的なテクニックと捉え、コードをバージョン管理システムに残す際などには、#を使った正式なコメントに修正するのが望ましいでしょう。
初心者がPythonでの複数行コメントアウトなどを効率的に学ぶには
複数行のコメントアウトをはじめとするPythonのスキルを効率的に習得するには、プログラミングスクールの活用が最も近道です。
スクールでスキルを高めることにより、今の仕事に活かしたり、副業として高単価な案件を受注できたりするだけでなく、Pythonエンジニアとして転職することも可能になります。
Pythonエンジニアは需要が非常に高いため、それに比例して年収も高くなる傾向にあります。
「今よりも年収を上げたい」「将来性の高い職種であるエンジニアへ転職したい」といった気持ちが強い場合は、プログラミングスクールでPythonの専門スキルを習得しつつ、ポートフォリオ支援や転職支援を受けてエンジニアへ転職する、という道を目指すのもよいでしょう。
なお、「Pythonに強く、受講生からの評判も良いプログラミングスクール」には、以下のようなところがあります。
- デイトラ
(※格安)
- キカガク
(※専門的)
- Aidemy Premium
(※受講コースが豊富)
その他、以下の記事でもPythonのおすすめスクールをまとめていますので、興味のある方は是非参考にしてください。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!
数あるスクールを徹底比較した結果、未経験から本気でプロを目指すなら、今の選択肢は「RUNTEQ」一択です。
- ✅ 給付金で実質13万円〜の圧倒的なコスパ
- ✅ 現場で通用する「本物の開発力」が身につく
- ✅ 受講生コミュニティの活発さが業界No.1
※無理な勧誘は一切ありません。相談だけでも価値があります。