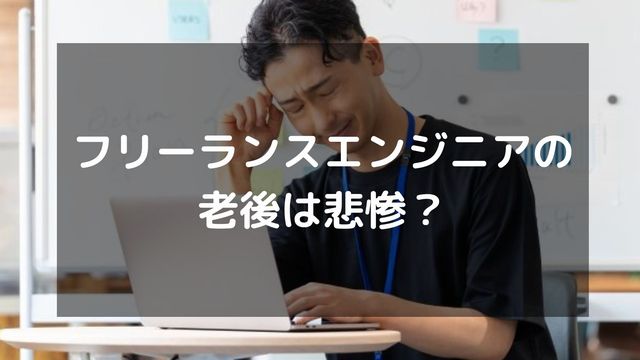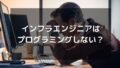フリーランスエンジニアという働き方は、自由で高収入を目指せる魅力的な選択肢です。
しかしその一方で、「老後は悲惨だ」という声を聞き、将来に漠然とした不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
確かにフリーランスエンジニアは、会社員と異なり、退職金や手厚い年金制度に守られていないのは事実です。
ですが、悲観する必要はまったくありません。
フリーランスには、フリーランスだからこそ活用できる有利な制度があり、計画的に準備を進めることで、安定した老後を築くことも可能なのです。
この記事では、フリーのエンジニアが直面する老後の現実から、具体的な資金計画、今すぐ始めるべき対策などについて詳しく解説していきますので、是非参考にしてください。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!
なぜフリーランスエンジニアの老後は悲惨だと言われる?

フリーランスエンジニアの老後が不安視されるのには、会社員との構造的な違いが原因です。
フリーランスは、会社員と比較すると、以下の項目で解説するような不利な部分があります。
退職金がない
フリーランスエンジニアには、会社員のような退職金制度が存在しません。
長年勤め上げた会社員が退職時に数千万円単位の退職一時金や企業年金を受け取る一方、フリーランスは自身でそれに代わる資金をゼロから準備する必要があります。
厚生労働省の「令和5年就労条件総合調査」によると、大学・大学院卒(管理・事務・技術職)の定年退職者の平均退職給付額は1,896万円にも上ります。
フリーランスエンジニアが、この金額をすべて自分で用意しなければならないと考えると、大きなハンデに感じられるかもしれません。
この「退職金がない」という事実が、老後が悲惨だと言われる最も大きな要因の一つです。
しかし、後述する「小規模企業共済」などを活用すれば、自分で退職金を作ることは十分に可能なので、過度に心配する必要はありません。
厚生年金を払い続けてきた会社員よりも年金が少ない
日本の公的年金は2階建て構造になっており、全国民が加入する1階部分の「国民年金(基礎年金)」と、会社員や公務員が加入する2階部分の「厚生年金」があります。
フリーランスエンジニアが加入するのは、原則として国民年金のみです。
そのため、国民年金と厚生年金の両方を受け取れる会社員と比較して、将来の年金受給額に大きな差が生まれてしまいます。
2025年度の国民年金の満額(40年間保険料を納付した場合)は、月額約6万8,000円、年額で約81万6,000円です。
一方で、厚生労働省の「令和4年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によると、厚生年金(国民年金を含む)の平均受給額は月額約14万4,000円です。
単純計算でも、月額で7万円以上、年額で90万円近い差が生じることになります。
この差が老後の生活に与える影響は非常に大きいため、フリーランスは、現役時代から意識的な資産形成が不可欠と言えるでしょう。
収入が不安定なので貯金しづらい
フリーランスエンジニアは、会社員のように毎月決まった給料が保証されているわけではありません。
景気の動向や、良い案件と巡り会えるかどうかなど、様々な要因に影響を受けて収入は大きく変動します。
収入が100万円を超える月もあれば、案件が途切れて収入がゼロになる月もあるかもしれません。
このような収入の波があると、毎月一定額を計画的に貯蓄や投資に回すことが難しくなります。
収入が良い時期に「今月は多めに使ってしまおう」と考えてしまうと、なかなか資産は積み上がりません。
また、将来の収入への不安から、大きな金額を投資に回すことを躊躇してしまう方もいるでしょう。
収入が不安定だからこそ、後述するiDeCo(個人型確定拠出年金)のように、半強制的に資産形成ができる仕組みを生活に組み込むことが非常に重要になります。
重い病気や怪我によって詰んでしまう可能性があるから
フリーランスエンジニアにとって、自身の身体は最大の資本です。
もし重い病気や大きな怪我で長期間働けなくなってしまった場合、収入が完全に途絶えてしまうリスクがあります。
会社員であれば、健康保険から「傷病手当金」が支給され、給与のおおむね3分の2が最長1年6ヶ月間保障されます。
しかし、フリーランスが加入する国民健康保険には、この傷病手当金の制度が(一部組合を除き)ありません。
つまり、働けなくなった瞬間から収入はゼロになり、貯蓄を取り崩して生活費や高額な治療費を支払う必要が出てきます。
十分な貯蓄がなければ、生活が一気に困窮し、キャリアの継続すら危うくなる「詰み」の状態に陥りかねません。
フリーランスエンジニアに必要な老後資金

フリーランスエンジニアが老後への不安を解消する第一歩は、不安の元となる正体、つまり「老後にいくら必要なのか」を具体的に知ることです。
ここでは、自分に必要な老後資金額を算出する方法と、具体的なケースに基づいたシミュレーションをご紹介します。
老後資金の計算方法
老後に必要な資金額は、非常にシンプルな計算式で算出できます。
基本的な考え方は、「老後の総支出」から「老後の総収入(主に公的年金)」を差し引くというものです。
(毎月の生活費 × 12ヶ月 × 老後の年数)-(年間の年金受給額 × 老後の年数) = 自分で準備する資金額まず、自身のライフスタイルから「老後の毎月の生活費」を想定します。
次に、「老後の年数」を決めます。
一般的には、65歳でリタイアし、平均寿命(男性:約81歳、女性:約87歳)まで生きると仮定し、20〜25年程度で計算することが多いです。
最後に、将来もらえる「年間の年金受給額」を差し引きます。
これは、日本年金機構の「ねんきんネット」に登録することで、かなり正確な見込み額を確認できるので、ぜひ一度試してみてください。
ケース別シミュレーション
それでは、具体的なモデルケースで必要な老後資金額をシミュレーションしてみましょう。
ここでは、65歳でリタイアし90歳までの25年間を老後生活と仮定します。
年金受給額は、フリーランスの平均的な金額として年間約80万円(国民年金満額)で計算します。
独身の場合
総務省の家計調査報告を参考に、比較的現実的な生活費でシミュレーションしてみましょう。
| 毎月の生活費 | 17万円 |
| 年間の総支出 | 204万円(17万円 × 12ヶ月) |
| 老後25年間の総支出 | 5,100万円(204万円 × 25年) |
| 年間の年金受給額 | 80万円 |
| 老後25年間の年金総収入 | 2,000万円(80万円 × 25年) |
| 自分で準備する資金額 | 3,100万円 |
このように、独身の場合でも3,100万円ほどを自力で準備しなければなりません。
夫婦の場合
夫婦の場合も、公的データに基づいた現実的な生活費で見直してみましょう。
ここでは、夫婦ともに国民年金に加入していると仮定します。
| 毎月の生活費 | 28万円 |
| 年間の総支出 | 336万円(28万円 × 12ヶ月) |
| 老後25年間の総支出 | 8,400万円(336万円 × 25年) |
| 年間の年金受給額(2人分) | 160万円(80万円 × 2人) |
| 老後25年間の年金総収入 | 4,000万円(160万円 × 25年) |
| 自分で準備する資金額 | 4,400万円 |
これらの金額は大きく感じられるかもしれませんが、これはあくまで公的年金のみを収入源とした場合の計算です。
次の章で解説する様々な制度をフル活用することで、この必要額を効率的に準備していくことが可能です。
フリーランスエンジニアの老後の資金対策
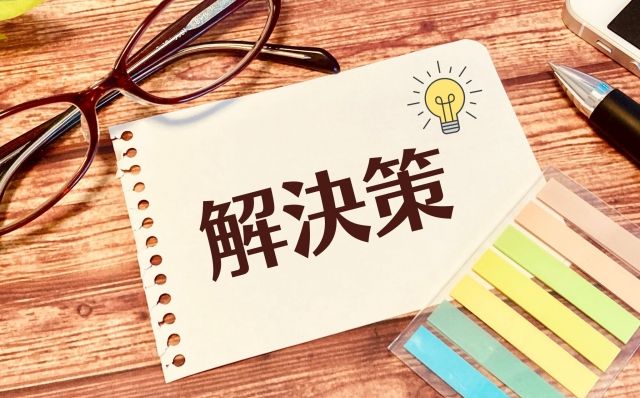
上記のシミュレーション結果で、老後に必要な資金額の大きさに驚いたかもしれません。
しかし、フリーランスには国が用意した節税・資産形成制度があります。
これらを賢く活用することで、老後を安定させることも可能です。
ここでは、絶対に知っておくべき6つの資金対策を、優先度の高い順にご紹介します。
小規模企業共済|フリーランスの退職金制度
フリーランスの退職金準備として、まず検討すべきが「小規模企業共済」です。
これは国が運営する制度で、個人事業主や小規模企業の経営者が、事業をやめたり退職したりした際に備えて資金を積み立てるものです。
最大のメリットは、掛金が全額所得控除の対象になることです。
掛金は月々1,000円から7万円の範囲で自由に設定でき、例えば年間上限の84万円を拠出すれば、その全額が課税所得から差し引かれます。
受け取る際も、一括で受け取れば「退職所得控除」、分割で受け取れば「公的年金等控除」という大きな税制優遇が適用されます。
デメリットとしては、加入から20年未満で任意解約すると元本割れしてしまう点が挙げられますが、長期的な退職金準備と割り切れば、これ以上ないほど有利な制度です。
iDeCo(個人型確定拠出年金)|最強の節税・資産形成ツール
「iDeCo(イデコ)」は、将来の年金を自分自身で準備するための私的年金制度です。
特にフリーランスエンジニアにとっては、小規模企業共済と並ぶ必須の制度と言えるでしょう。
その理由は、他の金融商品にはない圧倒的な3つの税制優遇にあります。
| 掛金が全額所得控除 | 小規模企業共済と同様、拠出した掛金の全額が所得から控除され、所得税・住民税が軽減される。 |
| 運用益が非課税 | 通常、投資で得た利益には約20%の税金がかかるが、iDeCoの口座内での運用益はすべて非課税。この効果は長期間になるほど絶大。 |
| 受取時も控除の対象 | 60歳以降に受け取る際も、「退職所得控除」または「公的年金等控除」が適用され、税負担が軽くなる。 |
フリーランスの場合、月額68,000円(年間816,000円)まで拠出可能です。
ただし、原則として60歳まで資金を引き出せないという強力なロックがかかる点には注意が必要でしょう。
しかし、これは老後資金を着実に貯めるという目的から見れば、むしろメリットと捉えることもできます。
新NISA|2024年から始まる新定番の資産運用
2024年からスタートした「新NISA(ニーサ)」は、iDeCoと並行して活用したい非課税投資制度です。
iDeCoとの最大の違いは、いつでも自由に資金を引き出せる柔軟性にあります。
新NISAのポイントは以下の通りです。
- 生涯非課税保有限度額:1,800万円まで投資が可能
- 年間投資枠:最大360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円)
- 非課税保有期間の無期限化:期間を気にせず長期運用が可能
- 売却枠の復活:一度売却しても、その分の非課税枠が翌年以降に復活する
iDeCoのような掛金の所得控除はありませんが、「運用益が非課税」という大きなメリットがあります。
老後資金だけでなく、住宅購入や教育資金など、ライフイベントに備える中期的な資産形成にも最適です。
まずはiDeCoの非課税枠を使い切り、さらに余裕資金があれば新NISAで積極的に資産を育てていくのが王道の戦略と言えるでしょう。
国民年金基金・付加年金|国民年金を手厚くする
「国民年金基金」と「付加年金」は、フリーランスの年金額の少なさを直接補うための公的な上乗せ制度です。
国民年金基金は、加入時の口数やプランに応じて将来の年金額が確定する制度で、iDeCoと同様に掛金は全額が社会保険料控除の対象になります。
終身年金なので、長生きするほどお得になるのが特徴です。
一方、付加年金は、毎月の国民年金保険料にプラスして月額400円の付加保険料を納めることで、「200円 × 納付月数」で計算される金額が将来の年金に生涯上乗せされる制度です。
例えば10年間納付すれば、年間24,000円(200円×120ヶ月)が上乗せされ、2年以上受け取れば元が取れる計算になります。
ただし、iDeCoと国民年金基金の掛金は合算で月額68,000円が上限となっており、両方に同時に加入することはできますが、どちらか一方を選ぶのが一般的です。
所得補償保険|働けなくなるリスクへの備え
資産形成も重要ですが、そもそも収入が途絶えてしまっては元も子もありません。
そこで重要になるのが、病気や怪我で働けなくなった際の収入減をカバーする「所得補償保険」です。
これは民間の保険商品で、医師の診断のもと就業不能と判断された場合に、毎月一定額の保険金が支払われる仕組みになっています。
傷病手当金のないフリーランスにとって、この保険はまさに生命線となり得ます。
保険料は年齢や職業、保障額によって異なりますが、月々数千円から加入できる商品も少なくありません。
万が一の事態に備え、生活が破綻するのを防ぐための「守りの対策」として、必須の備えと言えるでしょう。
年金の繰り下げ受給|長く働ける人におすすめ
公的年金の受給は原則65歳からですが、これを66歳以降に遅らせる「繰り下げ受給」という選択肢があります。
1ヶ月繰り下げるごとに受給額が0.7%ずつ増額され、最大で75歳まで繰り下げると、なんと84%も増額された年金を生涯にわたって受け取ることが可能です。
例えば、65歳で年間80万円もらえる人が75歳まで繰り下げると、年間の受給額は約147万円にもなります。
これは、健康でスキルもあり、70代でも現役として働き続けられる自信があるエンジニアにとっては非常に魅力的な選択肢です。
ただし、繰り下げ待機期間中は年金を受け取れないため、その間の生活資金を確保しておく必要があります。
フリーランスエンジニアとして少しでも長く働くためにやるべきこと

老後資金を準備する「守り」の対策と同時に、エンジニアとしての価値を高め、少しでも長く稼ぎ続ける「攻め」の対策も極めて重要です。
収入を得られる期間が長くなれば、それだけ資産形成に余裕が生まれます。
年を取っても勉強を怠らない
IT業界の技術革新のスピードは凄まじく、数年前に主流だった技術があっという間に陳腐化してしまうことも珍しくありません。
20代、30代と同じスキルのままでは、40代、50代と年齢を重ねるにつれて、より若くて安価な労働力に取って代わられてしまう危険性があります。
そうならないためには、常にアンテナを高く張り、新しい技術やトレンドを学び続ける姿勢が不可欠です。
AI、クラウド、データサイエンス、セキュリティといった需要の高い分野の知識をキャッチアップし、自分の専門領域と掛け合わせることで、自身の市場価値を維持・向上させることができるでしょう。
勉強会や技術コミュニティに積極的に参加し、インプットとアウトプットを繰り返す習慣をつけることも大事です。
下流だけでなく上流工程もこなせるようになっておく
プログラミングやテストといった「下流工程」のスキルだけでは、年齢を重ねると体力的に厳しくなったり、単価が頭打ちになったりする可能性があります。
長く活躍し続けるためには、より付加価値の高い「上流工程」のスキルを身につけておくことが有効です。
具体的には、顧客の要望をヒアリングして仕様を決める要件定義、システム全体の構造を考える設計、プロジェクト全体の進捗や品質、チームを管理するプロジェクトマネジメントなどが挙げられます。
これらのスキルは、経験とコミュニケーション能力が問われるため、むしろベテランのエンジニアにこそ求められる役割です。
コーディング能力に加えて、こうした上流工程の経験を積むことで、より高単価で年齢に左右されにくい案件を獲得できるようになるでしょう。
健康維持に人一倍気を使う
フリーランスエンジニアにとって、何よりも大切な資本は「健康」です。
どれだけ高いスキル・潤沢な貯金があっても、健康を損なって働けなくなってしまえば、すべてを失いかねません。
会社員と違って、休んでも誰も給料を保証してはくれないのです。
特に長時間座りっぱなしになりがちなエンジニアは、運動不足による生活習慣病や、腰痛、肩こり、精神的なストレスといった問題を抱えやすくなります。
以下のようなことを意識的に生活に取り入れ、自己管理を徹底してください。
- 定期的な運動習慣(ウォーキング、ジム、ストレッチなど)
- バランスの取れた食事と十分な睡眠
- 年に一度の人間ドックや健康診断の受診
- ストレスを溜め込まないための趣味やリフレッシュ方法の確保
健康への投資は、将来の自分に対する最大のリターンをもたらす投資です。
コストを惜しまず、自分の身体をメンテナンスすることを最優先に考えましょう。
常に人脈を広げ続ける
フリーランスとして安定して案件を獲得し続けるためには、技術力だけでなく「人脈」も非常に重要な要素となります。
一度仕事をしたクライアントやエージェントと良好な関係を築いておけば、次の案件を優先的に紹介してもらえる可能性が高まります。
また、エンジニア同士の横のつながりも大切にしてください。
勉強会やカンファレンス、オンラインコミュニティなどに積極的に参加することで、最新の技術情報を交換したり、自分にはないスキルを持つエンジニアと協業したり、思わぬところから仕事のチャンスが舞い込んだりすることがあります。
人脈は一朝一夕に築けるものではありません。
現役で活躍しているうちから、誠実なコミュニケーションを心がけ、信頼のネットワークを地道に広げていく努力を続けましょう。
老後を心配するフリーランスエンジニアのFAQ

ここまで様々な対策を紹介してきましたが、それでもまだ具体的な一歩をどう踏み出せばいいか迷う方もいるかもしれません。
ここでは、老後を心配するフリーランスエンジニアが抱きがちな疑問について解決していきます。
まずはどの資金対策から行うべき?
多くの選択肢があって迷うかもしれませんが、優先順位をつけるなら以下の順番がおすすめです。
【最優先:「小規模企業共済」と「iDeCo」】
この2つは、掛金が全額所得控除になるという絶大な節税効果があります。
これは国がフリーランスに与えてくれた最大の特典と言っても過言ではありません。
まずはこの2つの制度の加入を検討し、可能な限り上限額まで拠出することを目指しましょう。
【次にやるべきこと:新NISA】
小規模企業共済とiDeCoの枠を使い切ってもなお資金に余裕がある場合、次に活用したいのが新NISAです。
運用益が非課税になるメリットは大きく、いつでも引き出せる流動性の高さも魅力です。
【守りの備え:所得補償保険】
上記と並行して、万が一の就業不能リスクに備える所得補償保険の加入も検討してください。
資産形成の土台を守るための重要な保険です。
老後への備えは何歳から始めるべき?
結論から言うと、「気づいた今が始めどき」です。
資産形成は早く始めるに越したことはありません。
なぜなら、利息が利息を生む「複利」の効果を最大限に活用できるからです。
例えば、同じ目標金額を目指す場合でも、20代から始めれば毎月の積立額は少なくて済みますが、40代からだとより多くの金額が必要になります。
50代から備え始めてももう遅い?
50代からでも、決して遅くはありません。
もちろん、20代や30代から始めるのに比べれば、準備期間が短いというハンデはあります。
しかし、50代からでも打つ手はたくさん残されています。
これまで解説してきた通り、「iDeCoの活用」「NISAのフル活用」「年金の繰り下げ受給」などを駆使しつつ、50代エンジニアならではの経験を活かした高単価案件を獲得し続ければ、資産形成には十分間に合います。
まとめ
フリーランスエンジニアの老後は、準備を怠れば「悲惨」なものになる可能性があります。
しかし、裏を返せば、正しい知識を持って計画的に行動すれば、安定した老後を過ごせる可能性が高いということにもなります。
この記事で紹介した内容を踏まえ、ぜひ老後に対して正しく備えるようにしてください。


実務未経験エンジニアでも希望の転職先を見つけやすい!!
週1~3日からできる副業案件多数!!
フリーランス案件の単価の高さは圧倒的!!